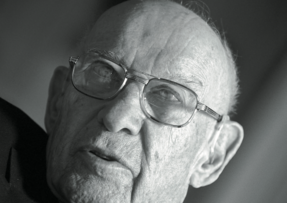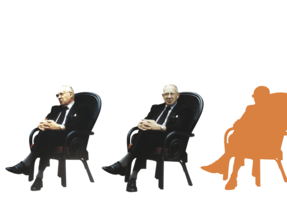-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
経営科学はこのままではいけない
しばらく前、ある経済団体から「経営科学と事業計画」というテーマで講演を頼まれた。
これがきっかけとなって、オペレーションズ・リサーチ(OR)、統計理論、統計的意思決定論、システム論、サイバネティックス[注1]、データ処理、情報理論、計量経済学、管理会計、会計論など、ここ4、5年に発表された経営科学関係の文献を総ざらいすると共に、経営科学が応用されている企業活動──社内スタッフか社外コンサルタントによるかにかかわらず──についてもつぶさに観察してみた。
その結果、私は経営科学への期待は当然のものだと感じた。たしかにマネジメントには「アート」の部分が残る。経営者や企業の業績は、経営者の才覚や経験、ビジョン、決断、経営スタイルなどに左右される。ただし、それは医学にもいえることである。
そして医者と同じく経営者も、マネジメントに関する知識が豊かであり、造詣が深いほど成果を上げられる。しかもこれらの知識が、一つの体系として成立しうることは、これまでの経営科学の歩みからいって明らかである。
ところが同時に、私は経営科学への懸念も持った。たしかに可能性はある。だがその可能性は実現しないかもしれない。我々は、経営者や起業家が必要とする知識やコンセプト、体系の代わりに、テクノクラートが喜ぶような経営手法が詰まった道具箱を開発しているだけなのかもしれないのである。
今日、経営科学の仕事のほとんどが、品質管理や在庫管理、倉庫の立地、物流管理、機器設置、保守管理、注文処理など、すでに開発済みの職能別の手法を精緻化することに終始している。これらのいずれもが、IE(インダストリアル・エンジニアリング)、原価会計、工程分析の延長線上のものであり、製造、マーケティング、財務の部分的な改善に関するものだ。
事実、企業組織のマネジメント、たとえば、リスクや意思決定に関する研究にしろ、体系にしろ、そのようなものは存在しない。私の目には、マサチューセッツ工科大学による産業動向プログラム[注2]と、ゼネラル・エレクトリック(GE)によるOR研究の2つしか入らなかった。
残念ながら、今日の経営科学は──文献的にも、実験的にも──原理ではなく手法に、意思決定ではなく手順に、その効果よりもツールとして、全体のパフォーマンスではなく部分の効率に目を奪われている。