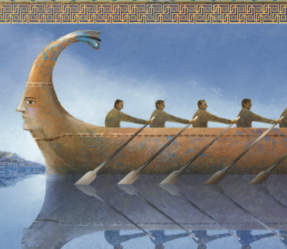-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
情報系プラットフォームと人事系プラットフォームとの整合を図る
「当社の建物はライバルと何ら変わらない。設備も大差ない。また当社の紙幣の色が濃いわけでもない。それでもアライドシグナルが他社と一線を画するのは、社員とその知識による」
アライドシグナル(現ハネウエル)の社長兼COO(当時)である、フレッド・ポウゼスの言葉である。1991年、ゼネラル・エレクトリックでジャック・ウェルチのパートナーを長らく務めたローレンス・ボシディがCEOに就任し、同社は堅調に増収増益を続けてきた。変革に当たってはさまざまな施策が講じられたが、その中核となったのが「ラーニング・リーダー」というコンセプトである。すなわち、9つの事業ユニットの枠を超えて全社員の能力を開発し、組織学習を体系化することを、アライドシグナルの全ビジネス・リーダーのミッションとしたのである。
その際、「社員の知識や能力を有効活用するにはどうすればよいのか」「社員がその知識や能力を広げるにはどんな施策が有効か」「社員をより顧客志向へ駆り立てる組織の要件とは何か」「キャリアアップを望む社員には、どのような能力を開発させるべきか、あるいは別のアプローチが存在するのか」といった問いかけが繰り返された。
このアライドシグナルの取り組みは、教育研修といったOff-JTを改善したり、拡充したりすることを意味しない。同社CLO(最高教育研修責任者)のドニー・ラメルによれば、成人の70%はやりがいのある仕事に従事している時に学習する、20%はだれかとコラボレーションした時、特に手本となる社員や優れたコーチから学ぶ、そして10%が研修やワークショップで学習するという。
そこでアライドシグナルでは、教室よりもむしろ現場で学習できる仕組みをデザインすることに力点を置いた。すなわち、継続的学習を奨励する「プラットフォーム」を構築することに焦点を絞ったのである[注1]。
人間が本来「学習する動物」であることは、幼児期の成長プロセスを見ても明らかだろう。幼児はだれに教わるでもなく、旺盛な好奇心と学習意欲を発揮して、社会生活に必要な知識や知恵を学んでいく。そのエネルギーが成長と共に減退していくのは、生来の好奇心や学習意欲が阻害される環境に置かれてしまうからだ。
したがって、これら知的モチベーションを喚起し奨励するメカニズム、その成果を集積してシナジーを生み出し、活用するメカニズムを適切に設計できれば、社員の能動的な学習を促し、そこで得られた知識や能力を組織能力へと昇華できるはずである。現実にそのよう組織は存在しており、概して次のような特徴が顕著である。