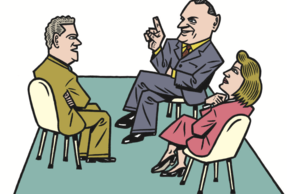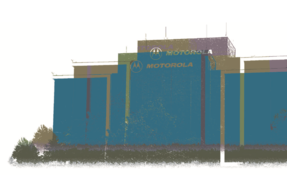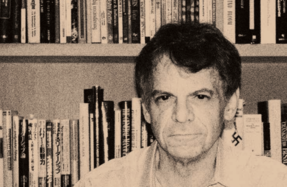-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
クロトンビルに始まり
いまeラーニング・ハブへ
現在、多国籍企業では、知的資本の重要性に着目し、かつてない革新的な手法で社員教育に取り組むようになってきている。この流れのなかで台頭してきたのが「企業内大学」である。
これは「ビジネス上のニーズを満たす教育手段すべてを統合・企画・開発・実施する戦略的な中核機関」と定義できる。アメリカの企業内大学は、自社の社員に知識を授けるだけにとどまらず、バリューチェーンのメンバー(顧客、サプライヤー、流通企業、パートナー企業など)をも対象に発展してきた。
最初の企業内大学は、1953年、トップ・マネジメントの基礎訓練キャンプとして、クロトンビルに発足したゼネラル・エレクトリック(以下GE)のリーダー研修センターだといわれている。
その後60年代には、「ディズニー大学」とマクドナルドの「ハンバーガー大学」が続いた。今日では全世界で約2000の企業内大学が存在するに至ったが、このペースで増え続けるとすれば、2010年にはアメリカの一般大学の3700校を超えてしまうことだろう。
この2年ほどで、企業内大学はウェブを利用した「学習ハブ」へと移行し、自社の学習プログラムへのアクセスはもちろん、各種のeラーニング・サービスやオンライン・ビジネススクールともリンクするようになった。ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンの「能力開発センター」(Center for Performance Excellence)は、この種のオンライン学習ハブの典型である。
同センターでは、各地に散らばる自社スタッフ1万1000人を対象としており、社員1人当たり約5500ドルのコストをかけて、600種類のeラーニング講座、一般大学のエグゼクティブ教育プログラムへのアクセス、オンライン図書館とのリンク、キャリア・センターなどを用意しているほか、エグゼクティブからの個人指導を求めることもできる。
ブーズ・アレン・アンド・ハミルトンのような学習ハブは、企業内学習の新しい顔となった──ただ学習の機会を与えるだけでなく、社員、顧客、サプライヤーの間で、新しい知識の共有と創造をうながすのである。