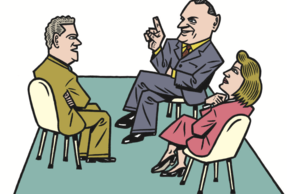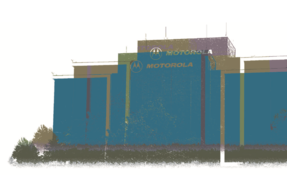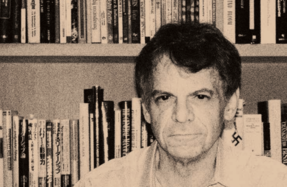-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
工員研修から始まった企業内大学への道程
モトローラでは、工場で働く従業員に3つのことを要求している。第1に、中学1年生程度の読み書きと計算ができ、これを中学2、3年レベルまで向上させなければならない。第2に、個人として、かつチームの一員として、基本的問題の処理能力がなければならない。
第3に、当社の職務規程に従わなければならない。その際モトローラでは勤務時間を、「発注した顧客の元に完璧な製品を納品するために必要な時間」と定義する。そのためには、週に50時間も60時間も働かなければならないかもしれない。単に物理的な労働時間を要求しているのではない。品質や成果を求めて働く意欲のある人材がほしいのである。
これらが掲げられたのは1990年頃のことである。それまでは、決められた定型業務さえこなしていればよかった。機械が故障しても、従業員は修理してもらうまで待っているだけ。品質管理は、出荷前に不良品を見つけるための単なるチェックにすぎず、従業員とマネジャーにとって、仕事は観察と経験と試行錯誤によって覚えるものだった。
研修も、従業員が学校や大学で習ったはずの基礎的な数学や国語の知識に加えて、新しいテクニックを教える程度のものであった。しかし、製造の概念と競争環境が激変し、その変化に対応していくなかで、従業員の研修と教育に関する考え方を改めざるをえないことに気づいたのである。
生産ラインの労働者は、自分の仕事と設備について深く理解しなければならないこと、マネジャーは、もし導入したい新しい手段や技法があれば、自ら範を垂れ、実践しなければならないこと、意識変革は全員参加の下で継続的に推し進めるべきこと、そして、これらは命令ではなく、教育によって初めて可能になることを学んだ。
ところが、変化に対応できるようになり、これから成果が上がっていくだろうと思った矢先、従業員たちの識字率が驚くほど低いことが判明した。多くが英語力に乏しく、百分率や分数といった簡単な計算すらできなかった。
ある工場では、サプライヤーが部品のパッケージを変更した結果、そこに書かれている文字ではなく、その色から判断して作業していたことすらあった。イリノイの工場では、現在形と過去形の区別がつかない移民の従業員がおり、監督者がいま起こっていることを話しているのか、過去に起こったことを話しているのかわからないという場面すらあった。