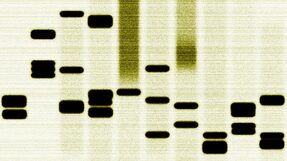-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
20年の時を経た破壊の理論
破壊的イノベーションの理論は1995年にHarvard Business Review(HBR)誌上で発表され、以来、イノベーションを起爆剤とした事業成長を考察するうえでの有用性が証明されている。この理論は、起業家精神に満ちた小規模企業のリーダーの多くから、さらにはインテル、サザンニューハンプシャー大学、セールスフォースドットコムなど、由緒ある大規模組織の経営幹部の多くから、「よき指針である」と称賛を得ている。
しかし、残念ながらこの理論は、称賛を得たがゆえの代償を支払わされているように思われる。広く普及したにもかかわらず、主な概念をめぐって誤解が蔓延しており、基本原則の応用もうまくなされない例が散見される。そのうえ、当初の発表内容が大きな注目を集めたため、以後の20年間における重要な改善がかすんでしまっているようだ。こうして破壊的イノベーション理論には時として、対処済みの欠点をあげつらうような批判が浴びせられている。
頭痛の種はこれだけではない。我々が見たところ、真っ当な書籍や論文を読まずに「破壊」を論じる人々があまりに多いのである。自分たちの目論見にとって都合のいいように「イノベーション」の概念を持ち出そうとして、「破壊」という言葉をいい加減に使ってばかりいるのだ。多くの研究者、著者、コンサルタントは、業界の再編や往時の成功企業の凋落をすべて、「破壊的イノベーション」によって説明しようとする。これはあまりに大雑把なやり方である。