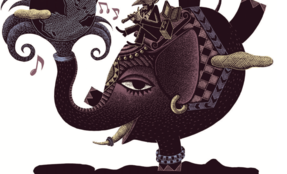-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ブラジルの近代化の歴史はまだ半世紀足らず
新興市場のなかでも、ブラジルはグローバル・ブランドに最も友好的といえるのではないか。ロシアや中国、インドなどのBRICs市場ではとても考えられないくらいグローバル・ブランドに寛容であり、むしろ積極的に受容している。それは、ブラジルの国民性は、定義するにはあまりにさまざまだからである。
1882年にポルトガルから独立し、まだ200年足らずの歴史しかないブラジルでは、ヨーロッパ移民の子孫が権力の中枢を握り、20世紀中頃以降の経済成長の恩恵のほとんどを享受してきた。ただし、ブラジルの文化はけっしてヨーロッパの影響だけを受けているわけではなく、さまざまな民族の文化に根差している。また、アメリカ大陸は、個々の伝統や文化が発する光を集める、言わば凸面鏡のような特性を持ち合わせている。
元来ブラジルでは、輸入品は高級品と見なされ、消費者たちは、遠く離れた自国とは異なる環境や気候の下で生活する人々の感受性(これこそ輸入品の魅力であろう)に興味を抱き、喜んでプレミアム価格を支払う。
このように外国製品を喜んで受け入れるという文化的特性に加えて、ブラジルでは、奴隷制は1888年に廃止されたとはいえ、それゆえのプランテーション作物──おそらく日本の方々も、ブラジルが砂糖やコーヒー、ゴムなどの原産国として有名なのはご存じだろう──を主に生産する農業国であり、いわゆるモノカルチャー経済が続いてきた。
このような状態から脱したのは比較的最近のことで、ブラジルに都市社会が形成されたのは20世紀中頃以降である。つまり、人口1億9000万人を擁し、日本の約22.7倍に相当する854万7400平方キロメートルというこの広大な国に、外資を誘致するための優遇政策が導入されてからだ。
ブラジル政府はまた、工業化を加速するために、利益の本国送金に関して非常に有利な条件を提供すると共に、外国為替取引についてもいっさい規制していない。これらのかいがあって、ブラジルの都市部は急速な成長を遂げた。1940年から2000年の間に、都市人口は1100万人から、何と1億3500万人に拡大している。
新世代の都市生活者たちは、まず「三種の神器」であるテレビ、冷蔵庫、洗濯機を手にし、次いで自動車やジーンズなどを購入した。しかも彼ら彼女らは、最初から有名な外国ブランドを選んだ。これらのブランドによって、マーケティング・キャンペーンなるものがブラジルでも一般化するようになった。
また、これらブランドの現地法人はほどなく、関税障壁のために完成品の輸入は高くつく一方、原材料の輸入は非課税であるという税法の間隙を衝いて、現地価格で提供し始めた。