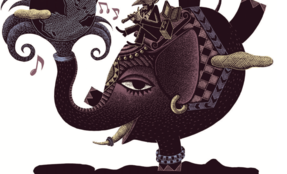-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ロシアへようこそ
でも、十分気をつけて
かつてウィンストン・チャーチルは、ロシアを「謎に包まれた謎のなかの謎」と評した。昔のロシア映画に、主人公が日本女性と恋仲になるという話がある。彼女を愛しているが、なかなか理解できない。ついには「まるで火星から来たような女性だ」と言う。
欧米人同様、ジェームズ・クラベルの『将軍[注1]』を読んで、初めて日本文化に触れたというロシア人は多い。この小説が、日本の「戦国時代」、それも16世紀から17世紀にかけての日本の精神を正しく描いているかどうかを論じられるのは、もちろん日出ずる国の人々だけである。いずれにしても、『将軍』が異文化との遭遇をみごとに描いていることは相違ない。
小説の主人公、船長代理を務めるイギリス人航海士、ジョン・ブラックソーンは仲間と一緒に日本のある海辺に流れ着く。そこで出会ったのは、奇妙な衣服をまとい、見たこともない食べ物を口にし、自分のものであれ他人のものであれ、人間の命など露ほどにも思わない不思議な人たちだった。そう、ブラックソーンたちの目に映ったのは、まさに野蛮人の集団だったのだ。
その一方、異人たちが日本人たちに与えた印象も同じくらいひどいものだった。日本人たちにすれば、金髪碧眼のヨーロッパ人は醜い怪物のようだった。彼らは死肉を食すばかりか、何週間も風呂に入らないため、ひどい悪臭を放っていた。主人公が日本での生活を理解し始めるのは、日本で暮らし、その言葉を覚え、日本人とその習慣について学んでからのことである。
やがて日本という国の内なる調和を理解した主人公は、立身出世を遂げ、侍の身分を得て、やがて旗本の地位も授かる。ちなみに、このモデルは、徳川家康の友人であり、顧問でもあった三浦按針こと、ウィリアム・アダムズである。同じように日本人の側も、アダムズの行動の論理を理解し、才能あふれる知識人として認めて、初めて彼という人間を尊敬するようになる。
言うまでもなく、いまは現代である。グローバリゼーションとITのおかげで、さまざまな文化が行き交うようになった。我々ロシア人も、日本の映画や文学に親しんでいる。モスクワには和食の店が何軒もある。街には日本車が走り、家庭には日本製の家電製品がある。にもかかわらず、日本のことはほとんど何も知らない。他国で成功するには、その国を理解しようと努め、公式非公式を問わず、その国独特のルールとその内なる論理を身につけなければならない。
ゴールドマン・サックスの予測によると、ロシアのGDPは2004年の5827億ドルから2025年には2兆3120億ドルへ成長し、1人当たりGDPも4086ドルから2万2615ドルへ拡大するという。
この予測は、ロシアに進出し始めた企業にすれば、何とも頼もしい数字である。しかし、成功にはリスクがつきまとう。ハイ・リターンにはハイ・リスクが伴う。ロシアでは、外国企業の行く手には、さまざまな危険が待ち受けている。それは大きくは3つのリスクに分けられ、相互に絡み合っている。言わば「三頭竜」といえよう。