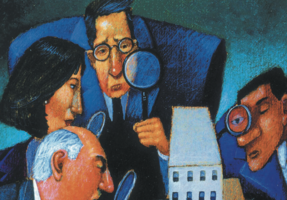-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
なぜ買収にも提携にも失敗してしまうのか
実は、企業戦略の中核をなす課題の一つには、やっかいなジレンマが隠されている──。
持続的成長がますます困難になるなか、売上高や利益を向上させる手段として、また株価を押し上げる一策として、買収と提携が利用されてきた。この傾向は、先進国において最も顕著といえる。
たとえば、1996年から2001年の間に、アメリカ企業が発表した買収および提携は、それぞれ7万4000件、5万7000件という膨大な数に上る。このことは、先の6年間、CEOは毎日ざっと1時間に1件ずつ、買収と提携の契約書に署名したことになる。その結果、連結ベースの買収額は急増し、12兆ドルに達した。
しかしその後、合従連衡のペースは鈍っていく。アメリカの調査会社、トムソン・フィナンシャルのデータによれば、2000年には1万2460件の買収と1万349件の提携が結ばれたが、2002年はそれぞれ7795件と5048件にとどまった。
ところが、企業成長への意欲が高まるにつれて、合従連衡の優先度が再び上昇している。2003年の買収と提携の件数は8385件、5789件と、いずれも前年実績を上回ったことがこのことを裏づけている。
ただし、なかなか解決しがたい問題が一つある。つまり、買収と提携はまず失敗する。少数の成功例はあるものの、買収は一般的に株主価値を破壊するか、何の足しにもならない。提携も株主価値をほとんど生み出さない。
『ストラテジック・マネジメント・ジャーナル』誌に掲載された3件の最新調査によれば、買収を仕掛けた企業の株価は、発表から10日間で0.34~1%下落する。なお、被買収企業の株価は平均30%上昇することから、価値の大半はそちらの株主の懐に入ると考えられる。