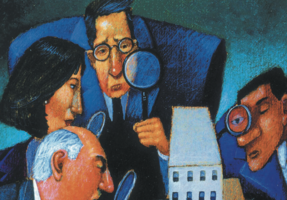-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
戦略的提携への誤解
ライバル同士がコラボレーションするのが流行っている。ゼネラルモーターズ(GM)とトヨタ自動車は共同生産し、[注1]シーメンスとフィリップスは半導体を共同開発し、キヤノンはイーストマン・コダックに複写機を一緒に供給し、フランスのエレクトロニクス・メーカー、トムソンと日本ビクター(JVC)はビデオ・レコーダーを一緒に製造している。
しかし、我々が「競争的コラボレーション」と呼ぶ、たとえばジョイント・ベンチャー、アウトソーシング、ライセンス契約、共同研究などの広がりは、長期的に見ると、その結末に不安を抱かせるものだ。
戦略的提携は概して、それが2社の場合、パートナーの一方を弱体化させるにもかかわらず、対外的には両社の立場を等しく強化する。特にアジア企業と欧米企業の提携を見る限り、欧米企業に不利に働くのではないか。
実際、ハーバード大学教授のロバート B. ライシュとエリック D. マンキンは、コラボレーションは新しいライバルが低コストで技術を獲得し、市場に参入することを可能ならしめると言う[注2]。
にもかかわらず、コラボレーションを是とする論理が、これまでにもまして強調されている。新商品を開発し、新市場に浸透させるには多額の投資が必要なため、ほとんどの場合において、単独で進出する企業はない。
イギリスのコンピュータ会社であるICLは、富士通というパートナーがいなければ、メインフレームを開発できなかっただろう。モトローラも日本の半導体市場に新規参入するうえで、東芝の流通機能を必要とした。
時間という要因も決定的である。欧米企業はアジア企業と提携することで、生産性競争や品質競争において近道が拓かれる。
我々は5年以上にわたって、15の戦略的提携について内部調査し、そのほか何十という提携関係を観察してきた。これらの研究対象には、互いに競争しているアメリカ企業と日本企業、ヨーロッパ企業と日本企業、アメリカ企業とヨーロッパ企業のコラボレーションが含まれている(囲み「本調査の実施に当たって」を参照)。