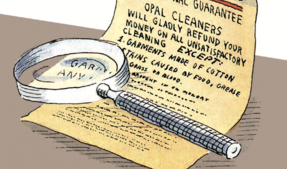-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
P&Gに残る伝説の文書
1930年代、大手消費財メーカーのプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)で、ニール・マッケルロイという新人マネジャーが石鹸の〈キャメイ〉の広告を担当していた。
会社はこの〈キャメイ〉を軽視し、最重要商品である〈アイボリー〉ばかりに力を入れ、多額の資金を注ぎ込んでいた。当然、〈アイボリー〉が主力商品と見なされ、〈キャメイ〉はたえず生き残りを考えなければならない有様だった。
この状況に落胆したマッケルロイは31年5月、3ページに及ぶ提言書を書いた。その主張は「P&Gはブランドを基盤とするマネジメント・システムに転換すべき」というものだった。同社の全ブランドに一定の予算と専任チームが割り振られ、市場で互角に渡り合えるようになったのは、これ以降のことである。
マッケルロイがP&Gのトップに就任した48年以降、この提言書は同社のみならず、あらゆる企業で「ブランド・マネジメントのABC」として読まれるようになった。このなかでマッケルロイは、P&Gではさまざまなブランドが経営資源と市場シェアを奪い合っていることを指摘した。各ブランドの担当者は、同社の他のブランドを犠牲にしてでも、担当ブランドを優位に立たせようとしているというのだ。
ただしマッケルロイは、これより先について論じてはいない。ブランドを廃止したり、手放したりする場合、どうすべきかについてはあまりはっきりとは言及していないのである。
マッケルロイがこの有名な文書を書いてから70余年が経った。しかし、いまだにブランドの取捨選択についてはマーケティングの教科書では取り上げられず、ツールとして用いられることも少ない。
新しいブランドの立ち上げや既存ブランドの活用、ライバル・ブランドの買収といった活動に、多くの資金と時間が注ぎ込まれている。チャネルやサブ・ブランドの拡大は言うに及ばず、商品ラインやブランドの展開によって、あらゆる市場で新しいニッチ市場を見つけては、そこに食い込もうと腐心している。つまり、顧客を引きつけようと複雑なマルチ・ブランド戦略を設計しているといえよう。
しかも驚くべきことに、折りに触れてブランド・ポートフォリオを見直す企業などほとんどない。ブランドの数や弱小ブランドのチェック、利益を生まないブランドを整理することもない。赤字ブランドがあっても、他の優良ブランドと統合する、あるいは売却・廃止といったことはなされないのだ。このせいで、ブランド・ポートフォリオには赤字ブランドは言うまでもなく、かろうじて黒字を維持しているブランドばかりが並んでしまう。
意外なことに、数あるブランドのうち、利益を生むものは一部にすぎない。我々が実施した調査によれば、利益に貢献しているブランドの数は年々少なくなっている。「20%のブランドが利益の80%を生み出す」という一般的な目安よりもさらに低いのだ。実際、ポートフォリオの全ブランドの20%以下に全利益の80~90%を依存している場合が多い。したがって、ブランド全体の80%以上は赤字、もしくは損益分岐点上にある。