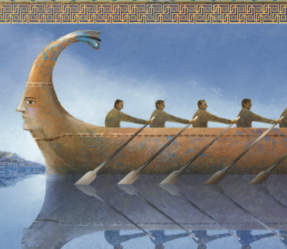-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
IBM復活の真相
「時代の申し子」だったはずのIT業界が失速するなか、IBMの活躍がひときわ際立っている。半導体に代表される先端技術、プラットフォームと呼ばれる基盤ハード・ソフト、そしてソリューション提供のカギとなるサービスなどを統合することで、他の専業プレーヤーの追随を許さない状況である。また、ITバブル崩壊後も、IBMはいち早く「eビジネス第2幕」を宣言し、顧客の利用価値に合わせたユーティリティ型コンピューティングへの移行を加速している。
10年前瀕死の重傷を負っていたIBMの復活劇は、ルー・ガースナー前CEOの近著に詳しい[注1]。それにしても、非連続な変化が常態化しているIT業界において、いかにして同社は過去10年間、先を正しく読み、圧倒的な優位性を築き続けることができたのだろうか。
たしかに、IBMの先見性には定評がある。情報と通信の融合をにらんでネットワーク・コンピューティング時代の到来をいち早く唱えたのは同社だった。また、2002年日本で一大ブームとなったユビキタス(遍在的)・コンピューティングも、IBMは「パーベーシブ(浸透的)・コンピューティング」というコンセプトで5年以上前から提唱してきている。
しかし、このような次世代ビジョンや事業コンセプトを打ち出すだけで優位性を築くことは困難だ。復活後のIBMが卓越している点は、これらのコンセプトを打ち出すだけではなく、いち早く実践に移すことにある。そして実践を通じて、顧客の本当のニーズや事業の採算性などを学び取り、戦略の細部を練り上げていくのだ。
たとえばインターネット黎明期にIBMは「IBMグローバル・ネットワーク」(以下IGN)の運営を通じて、世界最大のインターネット・プロバイダとなっていた。この経験から、ネットワーク事業そのもので通信会社を凌駕することは困難であること、そして、あらゆるものが情報処理レベルでつながるためにはミドルウエアこそが主戦場となることを学んだ。その結果IBMは、IGNをAT&Tに売却すると共に、ロータス、チボリ、インフォノミックスなどの先進ミドルウエア企業を矢継ぎ早に買収し、ネットワーク・コンピューティング時代のプラットフォーム・インテグレーターとしての橋頭堡を築いたのである。
また、2000年シドニー・オリンピックの公式サイトの運営を通じて、同社の中核ミドルウエア商品である「ウェブスフィア」の実績と信頼性を世界にアピールできたことも、eビジネス推進の大きな原動力となった。最近では、ユビキタス・コンピューティング時代の覇権確立に向けて、リナックス技術やXML技術への大規模なリソース・シフトを展開している。さらに後述するように、次世代技術と目されるオートノミック(自律型)・コンピューティングなどへの取り組みも積極的に行っている。