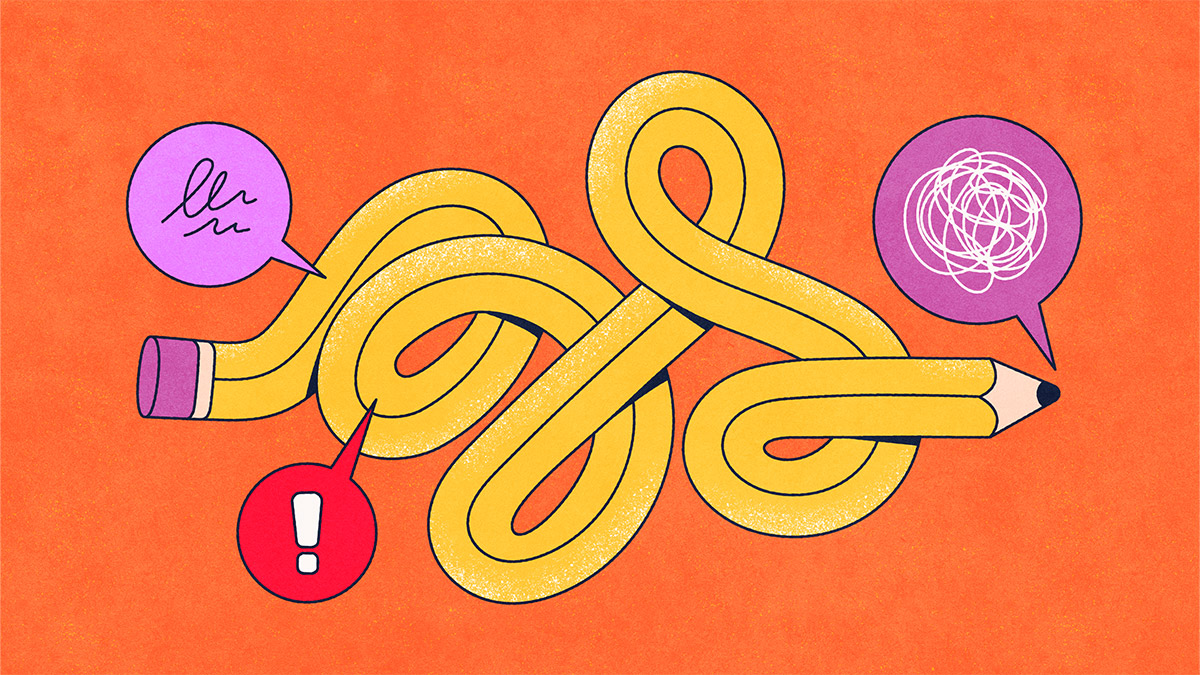
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
よかれと思った言動が実は間違っている
「私は、この業界がいまの厳しい状況を乗り切れると確信しています。そこで、チームのメンバーを安心させるために、意識的に、目立つ形でメンバーの成功を称賛するようにしています」と、あるテクノロジー企業で300人あまりの部署を率いるエリックは、2023年、筆者に語った。「ところが、それがうまくいっていないのです」
エリックの会社では従業員のレイオフを計画していないが、いくつかの競合企業は最近、大々的な人員削減に踏み切っていた。ニュースを見れば、不安をかき立てるような話題ばかりだ。エリックとしては、部下の不安を和らげたいと考えていた。特に気がかりだと感じていたのは、最近行われた従業員エンゲージメント調査の結果だった。その調査によると、エリックのチームのメンバーは、以前に比べて、質問をしたり、失敗を認めたりすることへの不安が格段に高まっているとわかったのだ。
この従業員エンゲージメント調査の結果を目の当たりにし、自分が部下たちに話していたこと(メンバーの成果を強調するストーリーを語っていた)を再検討し、数人の部下たちと話をした結果、それまで自分がやってきたことが意に反して、メンバーの不安をむしろ高めていたことに気づいた。
「突然、成果が強調して語られるようになり、私は不安になりました。この職場が非常に高い成果を要求する文化に移行しつつあり、一つでも失敗をしてしまえばクビになるのではないかと恐れるようになったのです」と、ある従業員は筆者に語った。別の従業員もこう語っている。「プロジェクトがうまくいっていないのは私だけなのではないかと感じる日もあります」
エリックは成功と成果にばかり光を当てるストーリーを語ることにより、意図せずして、あらゆることが常に円滑に運ばなくてはならないとメンバーが思い込むような環境をつくり出していた。その結果として、メンバーは、自身の努力がただちに成功を生まない時、恥の意識や無力感を抱くようになっていたのだ。
緊張が高まっている状況では、このようなコミュニケーションの破綻がことのほか起こりやすい。そして、見過ごせないのは、緊張が高まっている職場が増えていることだ。最近行われた世界規模の調査によれば、組織に雇われて働いている人の44%は、調査の前日に多くのストレスを経験したと答えている。
不確実な時期に、チームのメンバーに無用の不安を抱かせることを避けるためには、リーダーがコミュニケーションに細心の注意を払わなくてはならない。本稿では、よかれと思って行動しているリーダーによくある5つの過ちと、その過ちを回避するために取るべき行動を紹介する。
落とし穴1:成功だけを強調して語る
不確実性に直面している時、リーダーはメンバーの成功を強調して語ることによって、メンバーの気分をよくさせたいと考えがちだ。しかし、冒頭のエリックの事例が浮き彫りにしているように、リーダーが目覚ましい成功例ばかりを強調すると、失敗がゼロでなければ成功ではないというメッセージが伝わってしまう。そうなると、メンバーが何らかの障害に直面した場合、順調ではないのは自分だけだと思い込む可能性が高まる(障害に直面するのは避けて通れないことだ)。このような発想に陥ると、その人は周りの人たちにあまり助けを求めなくなる。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









