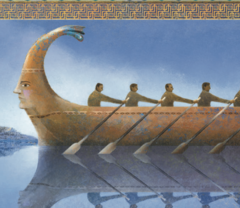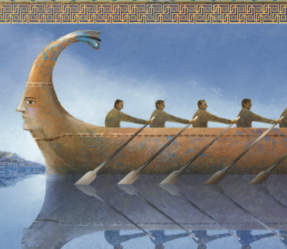-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
学習なくして改革なし
アメリカでは、生産性の高い強靭な組織をつくろうと変革運動がさかんである。それ向けのプログラムも各種開発されており、最新のものを導入しようとすれば、月に一度のペースで更新しなければならないほどだ。
しかし、いずれのプログラムも決定打に欠け、大した効果が得られないのも実態である。その理由は、改善運動に取り組んでいる企業のほとんどにおいて「継続的改善には組織学習へのコミットメントが必要である」という基本中の基本がきちんと理解されていないからである。
そもそも「学習」なくして、どうして「自己変革」できようか。問題を解決するにも、商品を開発するにも、リエンジニアリングするにも、まず新しい角度から物事を見直し、それから行動しなければならない。学習を怠るような組織では、個人も因習を繰り返すだけであり、仮に変化を起こすことができたとしても、それは表面的か、あるいは偶然の産物でしかなく、自ずと短命でしかない。
先見の明のある経営者、たとえば、アナログデバイスのレイ・スタータやチャパラル・スチールのゴードン・フォワード、ゼロックスのポール・アレアーらは学習と変革プログラムとの関係を承知しており、マネジメントの焦点を組織学習に置いている。
学界もこの傾向をサポートしており、「学習する組織」「知識創造企業」といったコンセプトを発表している。しかし半導体やエレクトロニクスなど、変化のスピードが速い産業ではこのような考え方をすでに採用しているが、まだまだあいまいで、他の多くの産業に至っては行動に移すレベルとは言い難い。
組織学習の定義とマネジメント、そして効果測定
とはいえ、このような混乱の責任の一端はアカデミズムにもある。学習する組織に関する議論は浮世離れしており、それゆえ理想論であり、時には半ば謎めいた用語で彩られる。
『最強組織の法則』を著し、学習する組織という言葉を世に広めたピーター M. センゲは、その著作のなかで学習する組織を「人々が継続的にその能力を広げ、望むものを創造したり、新しい考え方やより普遍的な考え方を育てたり、集団のやる気を引き出したり、人々が互いに学び合うような場」と定義している[注1]。このような目的を達成するためにセンゲは5つのツールを提唱している。