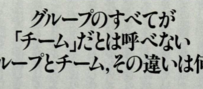-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
コラボレーションの増加で生まれる複雑な状況
企業を成長させる取り組みは、言わば究極のチームスポーツだ。さまざまな部署のデータ、テクノロジー、専門性を駆使しなくてはうまくいかない。とりわけ、テクノロジーのイノベーションとAIの進歩により、新しい収益源とビジネスモデルが続々と登場している時代には、活動を軌道に乗せるために部署の垣根を越えた大規模なコラボレーションが必要とされる。
コンサルティング会社のガートナーが400人を超すビジネスリーダーたちを対象に最近行った調査によると、大半の企業は常に5つもの複雑な取り組みを同時並行で実行しているという。たとえば、ある企業は、チャネル横断型の顧客体験を設計しようとすると同時に、セールス部門とマーケティング部門の統合を目指していて、さらには新しいデジタル成長戦略を構築しようとしていた。
このようなプログラムには、それぞれに5~8の部署が関わり、20~35人ものメンバーが参加する場合もある。こうした多様な取り組みに幅広いリソースが投入される結果として、社内には常に複雑性が充満するようになる。
このカオス状態に、ある程度の秩序をもたらす必要がある。ガートナーの調査に対して、組織のリーダーの78%は、筆者らが言うところの「コラボレーションの障害」を経験していると回答している。具体的には、会議の数や同僚からのフィードバックの件数が多すぎたり、意思決定の権限が不明確だったり、ステークホルダーの同意を得るために時間を要しすぎたりするのだ。
筆者らの研究によると、「コラボレーションの障害」が深刻な場合、企業は37%の確率で売上目標や利益目標を上回ることができず、部署横断型の取り組みが掲げる崇高な目標も達成できなくなることがわかった。また、大半の組織では、「コラボレーションの障害」が流行病のようにはびこっていた。
幹部レベルのすり合わせだけでは不十分
部署の垣根を越えたコラボレーションを破綻から救うことは可能なのか。その問いの答えは「イエス」だ。ただし、たいていの人が思い浮かべるような方法ではうまくいかない。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)