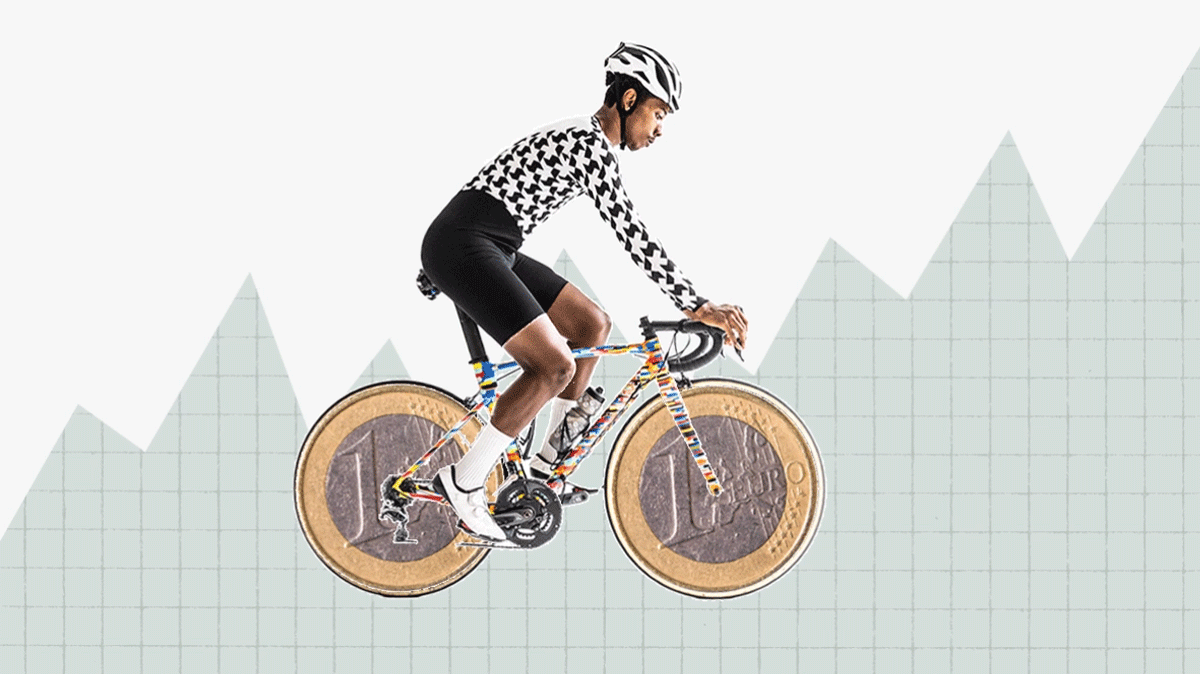
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
インセンティブは本当に従業員をやる気にするか
「いまの会社のインセンティブ制度が、とても大きなストレスになっています。そんな目標は達成できない気がしません。やる気どころか、大きなプレッシャーやストレスを感じます。上司は助けてくれるどころか、プレッシャーをかけるばかりです」
これは、ある従業員が会社の成果主義賃金制度(PFP)について漏らした言葉だ。PFPは、たとえば昇給や、個人またはチームのボーナス、利益分配、その他の金銭的インセンティブをパフォーマンスと結びつけることにより、高いパフォーマンスに報いるインセンティブ制度で、幅広く利用されている。しかし冒頭の従業員は、PFPによるストレスゆえにパフォーマンスが悪化して、最終的には仕事を辞めてしまった。
PFPは、従業員のモチベーションを高める最も効果的なツールの一つだと世界的に考えられてきた。米教育機関ワールド・アット・ワークの給与慣行に関する調査では、調査対象企業の93%が、少なくとも短期的なインセンティブを提供していることがわかった。しかし、その圧倒的な人気にもかかわらず、PFPによるストレスやプレッシャーが、パフォーマンスや創造性、従業員エンゲージメントの低下につながるという話もよく聞かれる。
PFPの普及と称賛と、筆者ら研究者が耳にするエピソードとの間に隔たりがあることを受け、従業員はPFPをどう感じているのかについて、筆者らは体系的に調べてみることにした。とりわけ、従業員がPFPを試練や脅威、またはその両方と見なしているかどうか、そして上司に対する認識がPFPへの評価に影響を与えているかどうかを業界横断的に調べた。
米経営学会誌に発表された筆者らの研究では、PFPは仕事上の大きなストレス要因となっていることがわかった。その影響は、仕事へのエンゲージメントやパフォーマンスにも及び、特にインセンティブが個人のパフォーマンスと結びつけられている時(PFP-I)に顕著だった。ただし、雇用者と従業員が制度を調整して、PFP-Iがパフォーマンスを妨げるのではなく、牽引できるようにする重要な要因も明らかになった。
よいリーダーのインパクト
PFP-Iに関する従業員の意見を調べるに当たり、筆者らは中国全土で、さまざまな業界に属する人たちを対象に、2つのフィールド調査を実施した。
第1の調査は、経理、庶務、エンジニア、人事、R&D、営業などさまざまな部門の従業員とその上司の組み合わせ247組を対象にした。彼らの勤め先は、ホテル、消費財、金融、IT、運輸、工業製品、教育など、さまざまな業界にまたがる234組織に及ぶ。また、参加した従業員は全員、実力に基づく昇給(PFP-Iの一種)の対象となっていた。
まず、これら従業員に、上司について2つのカテゴリーで評価をしてもらった。一方は適性(上司の能力、創造性、まとめ方などに対する見方を測定する質問をする)、もう一方は温かみ(親しみやすさ、信頼性、サポートなどについて質問する)だ。そのうえで、従業員らがPFP-Iを前向きな課題と見なしているか、それとも脅威と見なしているかを聞いた。また、彼らの仕事へのエンゲージメントレベルを聞き、その上司には従業員の仕事のパフォーマンスを評価してもらった。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









