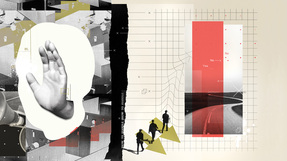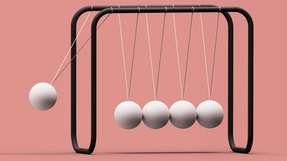-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
人は育てるものではなく機会を与えて育つもの
編集部(以下色文字):昨今の企業が直面する共通の課題として、人材難が挙げられます。新規採用がうまくいかなかったり、既存の従業員が辞めてしまったりと、自社が必要とする人材を確保できずに苦しむ企業は少なくありませんが、花王の場合はいかがでしょうか。
長谷部(以下略):花王に関して言えば、人の数が不足しているという意識はそれほどありません。ただ、特に最近の現象として、その時点ではベストだと考えられた人員構成がわずか2~3年で変わるようになり、変化に追随しきれていないことに対する課題感を抱いてはいます。
当社の場合、研究部門から事業部門に移るなど、部門の壁を超えて渡り歩く従業員は珍しくありません。そのような人たちは一つの部門では養えない経験知を身につけ、それが活きるようなキャリアパスを構築しながら活躍しています。その結果として人員構成のバランスの確保にも貢献してくれていますが、文系の社員に突然、「実験を担当してください」と言うわけにはいきませんから、そこにはやはり難しさが残ります。
また、人に関することで言えば、この会社で働いてくれる人たちの意欲が落ちてきたように感じています。ただし、その原因が必ずしも個人にあるとは言いきれません。人を育てるなどおこがましい、人は育つものである──。この考え方は、当社に根づいていると思います。土が悪ければよい木が育たないように、企業は成長の土台となる場を設けて、適切な機会を提供する必要があります。従業員の意欲が低下しているということは、我々がそのような機会を用意できていないということです。
花王の人材育成の原点には、よい仕事場が人をつくるという哲学があります。私は先人たちからそれが何より大切だと教えられてきましたし、私自身もそのように考えてきました。会社が適切な環境を提供していないにもかかわらず、従業員に問題があるなどと言うべきではありません。
若い人たちの問題を指摘する声はよく耳にしますが、長谷部さんは機会を提供できなかった側に問題があると考えるのですね。