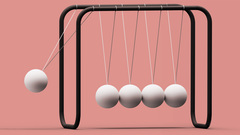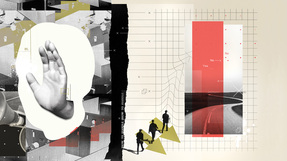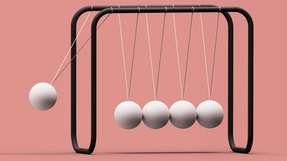-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
いまこそ従業員の「体験」に目を向けよ
いわゆる「人材獲得競争」はいまも激しく続いている。しかし、この状況下にあっても、企業はこれまで何十年も用いてきた採用と従業員維持の戦略を変えずにいる。そのアプローチは効果を発揮しておらず、戦略がない状況に比べれば従業員の勤続年数は多少は長くなっているかもしれないが、やはり従業員は辞めていくのである。
なぜ企業はそうした戦略を使い続けているのか。それは、逼迫した労働市場や容赦ないコスト削減のプレッシャー、ライバル企業による引き抜きといった難題に集中するあまり、より根本的な問題に向き合えていないからである。その問題とは、「満足のいく仕事上の体験を従業員に提供できていない」という問題である。人々が働き続け、そこで最善を尽くすには、意味のある仕事が必要だ。また、自分を評価し、尊重し、信頼してくれるマネジャーや同僚、キャリアにおける成長や昇進の機会も必要である。
企業のマネジャーや人事担当者らは、従業員の体験が採用や定着において重要であることを理解し始めている。しかし、そのあるべき姿や提供の仕方については、コンセンサスからはほど遠い。企業の中には、健康に関する取り組みや福利厚生に多額の資金を投じているところもあるが、その効果はまちまちだ。メンターや教育、育成のプログラムを試みている企業もある(多くが苦戦している)。これは価値のある取り組みだが、従業員がそれに何を期待しているかを認識できなければ、的確に実施することは難しい。
こうした、関連してはいるが一貫性を欠きがちな取り組みからは、いったん距離を置くべきだ。そして、いまこそ「体験」というより大きな問題に目を向け、解決できるようにすべきである。
筆者らは過去15年間にわたり、合計1000人以上の転職者の行動パターンを研究してきた。対象とした転職者は、あらゆる職位およびキャリアステージの人々だ。人種的にも多様で、幅広い職業、職種に就いていた。インタビューやアンケート調査、教室での議論、コンサルティング、コーチングのセッションなどを通じて、筆者らが繰り返し認識させられたのは、人々が仕事を辞めるのは、キャリアや人生で求める進歩を実現できていないからだ、ということである。
企業のニーズに沿った形で、従業員の進歩の探求をサポートすることによって、企業は従業員と企業の双方にメリットのある体験を従業員に対して提供できる。筆者らは定量的データセットを分析した結果、転職につながる進歩への探求は主に4種類あることを発見した。本稿ではその4つの探求について説明し、マネジャーがそれをどうサポートできるかを述べる。だがその前に、人材の問題による企業の利害について見ておこう。
根強くコストも高い退職問題
人材に関する問題を、今日の経済あるいは競争環境の厳しさのせいにすることはできない。新型コロナウイルス感染症の流行期には米国の退職率は史上最高となったが、企業はそのかなり前から、優秀な人材が知識やスキル、人的ネットワークなどを抱えたまま流出してしまうと嘆いていた。こうした退職には高いコストがつく。研究では、1人の従業員を失うコストは、平均でその人材の6~9カ月分の報酬に値すると推計されている。技術職や管理職では、その年収の2倍にもなる場合がある。