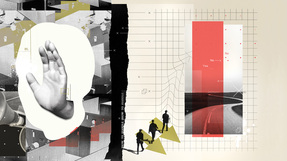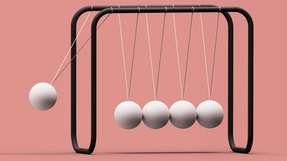-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
現在の従業員体験は機能していない
仕事の設計に関する研究が1世紀にわたり行われてきたにもかかわらず、マネジャーたちはポジティブな従業員体験を提供するのに苦戦し続けている。コロナ禍後の労働市場では、「静かな退職」や職場復帰方針をめぐる白熱した論争といったトレンドが現れ、それらは多くの従業員が職場での体験に満足していないという厳しい現実を露呈させた。
従業員たちは、忠誠心からではなく、必要性によってその役割に留まっているだけであり、このような持続可能性のない状況はエンゲージメントの低下につながる。
マネジャーが新たな視点を持ってこの問題に取り組み、プロダクトデザインと同じ方法で仕事を設計したらどうなるだろうか。ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)の教授を務めたクレイトン・クリステンセンの「ジョブ理論」(人は生活の中で特定のニーズを満たすために製品やサービスを「雇用する」〈hire〉と捉える)に着想を得て、マネジャーが「従業員は、何を期待して仕事を『雇用する』のか」と自問したならば、いったい何が起こるだろうか。
この数年、筆者の一人であるリンズリーは、大手テクノロジー企業のHRリーダーとして、また人気ポッドキャスト「ワーク・フォー・ヒューマンズ」の配信を通じて、「製品(プロダクト)としての仕事」というアプローチを探究してきた。もう一人の筆者、アニシッチは、学術研究や教育活動、コンサルティングの実践から、日々の仕事体験が従業員のウェルビーイングに及ぼす影響を探究してきた。企業が仕事を根本から再解釈し、従業員がみずからの労働力を対価として積極的に「購入する」〈buy〉ものへと変えることで、企業は大きな利益を得ることができると筆者らは信じている。そして、その仕事は、従業員が毎日購入したいと思えるように設計されているべきだ。
明確にしておきたいのだが、この考え方は、人事分野や先進的な企業の間で最近浮上し始めたばかりのものである。プロダクトデザインがよりよい顧客体験を生み出すことは実証済みだが、筆者らが知る限りでは、ここで提案している従業員向けモデルを完全な形で導入した雇用主はまだ存在しない。しかし、筆者らはこのプロダクトデザインの原則を使って従業員体験を再考している企業を見てきた。この考え方を提唱するのは筆者らだけではないのである。例を挙げてみよう。
フェイスブックの共同創業者でもあるダスティン・モスコビッツが共同創業したコラボレーションソフトウェア企業のアサナでは、マネジャーたちが、従業員に対して自分たちはどのような「リーダーシップ製品」を提供できているか議論している。同社では、辞めていく従業員にだけ退職面談を行うのではなく、現従業員に対しても定期的に満足度を尋ね、プロダクトデザイナーが顧客の要望を読み解こうとするように、従業員たちのニーズを理解しようと努めている。また、回答を記録するだけでなく、自社の職場をより魅力的なものにするための取り組みも行っている。
客室乗務員が乗客を飛行機から降ろす際に、「数ある航空会社の中から当社をお選びいただき、ありがとうございます」と伝えるように、共同創業者のジャスティン・ローゼンスタインによれば、アサナのマネジャーも同様のメッセージを定期的に伝えるよう推奨されているという。