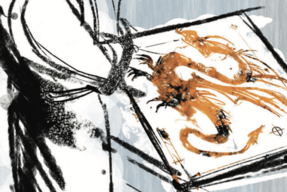-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
第一幕の名演技は
第二幕の成功を保証しない
CEOは電気椅子に座らされているようだ。CEOは、投資家が期待する業績を実現させるという重責を負っている。同時に、それぞれ利害の異なるステークホルダーたちも満足させなければならない。次々にCEOが交替させられるのも無理からぬことかもしれない。
ブーズ・アレン・ハミルトンがCEOの任期について調査したが、その結果によると、2005年にCEOが交替した例は、世界全体で15.3%、北米に限れば16.2%だった。
1995年時と比べて、世界全体で170%、北米では154%に拡大した。しかも2005年の調査では、CEO交替の3分の1が想定外の理由、すなわち業績不振による。
CEOが任期途中で解任されれば、言うまでもなくだれかが雇われる。それは、前任者が解決できなかった問題を解決できる能力を備えているはずの人物であり、当然かもしれないが、「会社の針路を変更せよ」、あるいは極端な場合には「沈没しかかっている船を救え」といった難題が課される。
取締役会がその新任CEOを信用したのは、目の前の問題、たとえば事業ポートフォリオの再編、コスト削減、市場シェアの拡大、規制当局との交渉など、その人が過去に解決した問題と似ているからである。
ある目的のために招聘したCEOは、彼もしくは彼女が得意な問題ならば、十分期待に応えてくれることだろう。事実、ボリス・グロイスバーグ、アンドリュー N. マクリーン、ニティン・ノーリアらがHBR誌に寄稿した「GE出身者でも失敗する時[注1]」で紹介されている調査を見ても、キャリアや経験をそのまま生かせる場合は成功しやすい。
しかし、手慣れた問題を解決した後には、必ずよく知らない問題が訪れる。すると、一芸に秀でているだけのCEOではとても太刀打ちできない。第一幕の成功劇の主役となった経験、スキル、気質が、第二幕では脇役にすらなれない例が多いのである。時には、第一幕を成功させた演技と、第二幕をハッピーエンドに導く演技はまったく別のものが要求されることすらある。
第二幕では、CEOには4つの選択肢がある。第1は、変化を拒否することである。この場合は、もちろん解任は避けられまい。第2は、新しいスキルが必要であることを認め、これを身につけることである。第3は、自分の欠点を認め、すすんで自分の役割に集中することである。第4は、自分のスキルや問題意識とミスマッチを起こしていることを認め、次の問題にふさわしい後継者を指名することである。
現実の世界で言えば、第1の例がヒューレット・パッカード(HP)のカーリー・フィオリーナであり、第2の例がメリルリンチのスタンリー・オニールであり、第3の例がグーグルのセルゲイ・ブリンとラリー・ペイジであり、第4の例がクエスト・ディアグノスティックスのケネス・フリーマンとなろう。
第1の選択肢以外は、いずれもCEOの「第二幕」における妥当な対策といえる。そしてこれら3つの方法には、観察力、内省力、謙虚さが求められるが、こういう資質は皮肉にも、最も必要な人たちほど備わっていないものである。