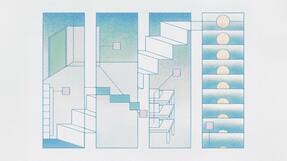-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
アシックスの強みを問い直す
編集部(以下色文字):アシックスはここ数年で急成長を遂げ、2024年12月期までの3期連続で過去最高益を更新しています。昨今の飛躍的な成長を実現できた要因は、どこにあるとお考えですか。
富永(以下略):近年の業績に目を向けると、2015年は好調でした。日本国内の売上げが土台となり、北米や欧州、中国、オーストラリアなどを中心にグローバルの売上げも伸びたからです。しかし、その年をピークに右肩下がりの状態が続き、新型コロナの影響もあって、2020年には赤字を計上しました。
その後、2021年以降の成長を実現する転機となったのは、現会長の廣田(康人)が2018年に入社してからリーダーシップを発揮し、大規模な改革を進めたことでした。そして、廣田による改革を象徴する取り組みの一つが、カテゴリー基軸の経営管理体制の導入です。
アシックスが当時抱えていた課題として、本社の製造や開発の現場と販売会社との間に大きな溝が存在していたことが挙げられます。業績がよい時は機能しても、業績が低迷すると、本社は「マーケティングが悪い」、販売会社は「製品が悪い」と批判し合います。目先の売上げを追うために、安易にエントリー商品を開発する、高価格帯の商品を意図していないチャネルで販売するといった事態も見られました。本社も販売会社もカテゴリーに対する理解が乏しく、確固たる戦略を持たない状態で戦っていたということです。
そこで、廣田はカテゴリー制を導入しました。商品のカテゴリー別に責任者を置き、製品開発から販売までを一貫して管理し、顧客、競合、販売チャネルに合わせた戦略を実行する体制へと変更したのです。
当社の製品は5つのカテゴリーに分かれます。ランニングシューズを展開するパフォーマンスランニング、テニスやバレーボールなどの競技用シューズを扱うコアパフォーマンススポーツ、機能性を備えながら日常生活でも着用できるスポーツスタイル、アパレル&エクイップメント、そしてオニツカタイガーです。現在はパフォーマンスランニングに注力し、そこが売上高の約50%を占めます。
アシックス側が載せたい機能を一方的に搭載したり、世の中の流行にただ乗っかったりするのではなく、コアコンピテンシーを問い直し、ふわふわしていた足元を固めてきた成果が花開いたのだと考えています。
アシックスのコアコンピテンシーはどこにあるといえますか。