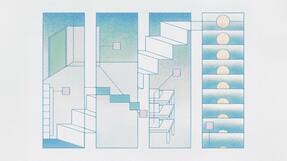-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
プロセスマネジメントに関する新たな思考法
大手食品会社のマースリグレーは自社のサプライチェーンをデジタル化するに当たり、AIとアナリティクスの強化に投資した。生産ラインのデジタルツイン(作業をリアルタイムでシミュレーションする仮想レプリカ)を構築し、そのデータを取り込んだ機械学習モデルが生産ラインの生産量を予測することで、過充填や無駄を削減した。
同社は「意思決定インテリジェンス」ベンダーのアエラ・テクノロジーと協力し、データの可視化を行い、予防保全に関する提言を作成し、一部の業務判断を自動化した。また、同社はベンダーのキナクシスを採用し、需給バランスの調整、請求書処理の自動化、トラックの運行効率を15%向上させる方法について従業員にアドバイスを提供するAIソフトウェアを導入した。このような改善を行った結果、マースリグレーは注文対応の迅速化を実現し、顧客サービス評価は数ポイント上昇した。
さらに最近では、マースリグレーは販売予測を行う機械学習モデルの構築に着手しており、これは工場長の生産計画策定に役立つと見込まれている。製造ラインでは、効率性と持続可能性の向上を目的として、スマートロボットや新たなAIシステムの導入が計画されている。要するに、同社はAIを活用して、幅広い業務におけるプロセスマネジメントを再構築してきたのだ。
プロセスマネジメントは、けっして複雑な概念ではない。その目的は、特定の成果を生み出すために、一連の作業がどのように組み合わせられているかを把握し、改善することである。また、プロセスマネジメントは多層的に適用できる。たとえば、個人の作業や少人数のグループ作業、部門内の主要業務に適用できるほか、全社的なプロセスや企業間をまたぐエンド・トゥ・エンドのプロセスでも有効活用できる。
適切に管理されたプロセスは、エラー率の低下、サイクルタイムの短縮、価値の低い業務の削減をもたらし、生産性が向上する。しかし、たとえAIを活用しても、プロセスマネジメントの大規模な導入は容易ではない。AIは、エンド・トゥ・エンドのプロセスよりも、特定の業務やサブプロセスに強みを発揮する。そのため、組織はプロセス全体の改善に向けて複数のAI活用事例を統合する必要がある。
プロセスマネジメントには、大規模なチェンジマネジメントが必要となる。具体的には、ステークホルダーの説得、従業員の再教育、多くの可動要素の統合が求められる。さらに、プロセスマネジメントは効率性の向上を目的として部門横断的に行われるため、従来の階層的なマネジメントと対立しがちである。また、1990年代初頭に大流行したビジネスプロセス・リエンジニアリング(BPR)は、結果的に多くのプロジェクトの失敗や無分別な人員削減を招き、プロセスマネジメントの評判を損ねた。人気が衰退したのも当然であろう。
それに加えて、企業は生産性向上を目指すうえで、AIをはじめとするITが期待に応えられていない現実にも直面している。経済学者のロバート・ソローが1987年に「コンピュータの時代が、あらゆる分野に訪れたことがわかる。ただし、生産性統計の分野を除いてだが」と指摘した言葉は、いまもなお当てはまる。企業は生産性の分析と向上のためにデータやITに莫大な投資を行ってきたものの、目立った成果を挙げられていない。大半の組織は、ITプロジェクトの投資利益率(ROI)を示す数値として、生産性指標を超えるものを把握できていないのが現状だ。
この状況を改善するには、プロセス思考の新たな手法が役立つ。