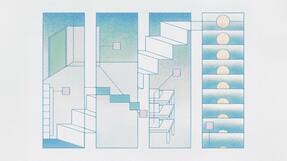-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
新たなマシン支援型プロセス
1940年代後半、大野耐一という名のエンジニアが、日本的理念である継続的改善、いわゆる「カイゼン」を柱にしたトヨタ生産方式(TPS)の体系化に乗り出した。このシステムにより、トヨタ自動車では、製造に携わるあらゆる職位の従業員から出された重要な提案に基づいて、小さな改良が絶え間なく行われるようになった。トヨタが選んだのは、大胆かつ革新的でリスクの高い試みによって業界に革命を起こすことではなく、漸進的だが徹底的な改善を進めることだった。
同社は現在、世界最大の自動車メーカーであり、トヨタ生産方式は企業におけるプロセスマネジメントの手法としてモデルであり続けている。この生産方式とともに生まれたいくつかの有名なコンセプトは、いまもなお現役だ。たとえば、従業員エンパワーメント、徹底した原価低減の実践、総合的品質管理(TQM)、ジャスト・イン・タイム、なぜなぜ分析、データ駆動型プロセス、自動化(オートメーション)に人間の知恵や工夫を取り入れた「ニンベンのついた自働化」などである。
オペレーションのデジタル化が進むにつれて、AIをはじめとする先進技術で強化されたカイゼンが、あらためてプロセスマネジメントの形を変えようとしている。いまや自然言語インターフェースなどの機能のおかげで、専門職以外の従業員でも生成AIにアクセスできるようになり、これが規模の大小を問わず、プロセス変革を加速させている。
AIのサポートがあれば、従業員は非構造化データを含むあらゆる種類のデータを統合できる。従来は意味がわからなかった大量の数値情報からワークフローの改善につながるインサイトを導き出すことで、継続的なパフォーマンスの向上、無駄の削減、より高い品質の達成につなげることができる。
一般には人間が生成AIに取って代わられると思われがちだが、カイゼン2.0はそうではなく、人間を新たなマシン支援型プロセスの中心に置くことにより、昔から多くの経営理論が目指してきた目標、すなわち「事業変革を全従業員の手に委ねる」ことを実現しようとしている。
しかし、ビジネスプロセスの刷新を成功させることは簡単ではなく、チャットGPTに監査の流れを尋ねるのとはわけが違う。改善を加速させるために、リーダーはアルゴリズムを用いて再設計するのに機が熟しているプロセスはどれかを把握し、他社が生成AIをどのように改善に活かしているかを理解する必要がある。
本稿では、テクノロジーとイノベーションについてクライアントに助言してきた筆者らの数十年の経験を踏まえて、最も優れた企業がどのように生成AIを導入しているかを説明する。また、完全に自動化されたエージェントが目標達成に向けて自律的に動き、戦略を採用して、環境を分析し、複雑なタスクを完遂するようなカイゼンの未来についても紹介する。ただし、どのテクノロジーを導入する場合にもいえることだが、生成AIの成功、そしてAIでビジネスプロセスを改善する能力のカギは、今後も人間が握り続けるだろう。
従業員エンパワーメントの全社的な実現
自動車生産から生命科学、消費財に至るさまざまな業界、そしてR&Dから製造、サプライチェーンマネジメントに至るさまざまな機能部門において、生成AIを用いた新たな形の従業員エンパワーメントが進んでいる。たとえばメルセデス・ベンツでは、製造現場、サプライチェーン機能、ソフトウェア設計といった分野でこれが実現している。
同社のMO360データプラットフォームは、世界各地の乗用車生産工場をクラウドに接続させることによって、生産とサプライチェーンにまたがるオペレーションの透明性と予測可能性を高め、世界規模のAI展開と分析を可能にする。2024年前半までメルセデス・ベンツ・グループのCIOを務めていたヤン・ブレヒトは以前、次のように語っている。