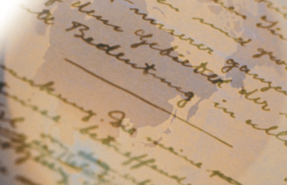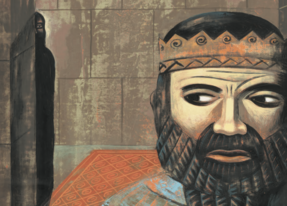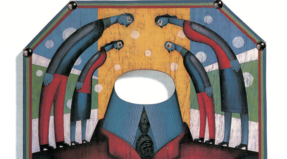-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
変革の波は取締役会にも押し寄せている
企業も家庭も同じである。甘やかしたことがとんでもない非行の原因になりかねない。近年の企業不祥事によって、あまりに消極的、あまりに寛大、あまりに鈍感な取締役会が存在することが白日の下にさらされた。
その結果、コーポレート・ガバナンスにまつわる義務が厳しくなり、財務報告の裏づけを取ったり、取締役会の構成を変えたり、コンプライアンス(遵法義務)を徹底するためにあわてて、あれこれやり出したところだ。しかしそれだけでは、ただ「法律を守りなさい」と当たり前のことを念押ししたにすぎない。もちろん自慢にもなりはしない。
コーポレート・ガバナンスを高めるカギは、まず取締役会と、経営陣(直接の業務執行に当たるCEOをはじめとする経営陣)との協力関係にあり、次に取締役会内の人間関係にあり、最後に取締役一人ひとりの能力、誠実さ、そして熱意にある。
もちろん、これらのことは法律のらち外のことである。すでにほかの論者も指摘しているとおり[注]、悪名を馳せたスキャンダル企業でも不正予防策として、いま言われているような改革には着手していた。
取締役会が、最大公約数的な対策では満足しないという気概を持っているならば、外圧による義務を果たすだけで安閑としてはいられない。もっと大所高所から考え、現実的な行動を実行しなければならない。目指すべき目標をはっきりさせ、取締役会の変革に必要な手段を手に入れるのだ。
この変革には長い時間がかかるだろう。だれでも知っていることだが、ほとんどの取締役会はいまなお、儀式と形式だけを重んじる紳士クラブ時代の遺物である。
またこれも当たり前だが、そもそも取締役会は経営陣を厳しくチェックする機関である。干渉にすぎることなく、何らかの価値を提供し、CEOを増長させることなく、その力を引き出さなければならない。
取締役会がこの理想像にたどり着くには──過去数十年間にわたり、いろいろなチームを見てきた経験から申し上げれば──一つのチームとして機能することが絶対条件である。パフォーマンスに優れた取締役会とは、高業績チームそのものにほかならない。各種能力にあふれ、協調性に富み、各人が対等で、曇りのない目標をまっすぐ目指す。