
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「競争」と「価値の創造」の追究
私たちは社会の進歩を目指してさまざまな活動を行っているが、競争はその中でも最も強い力を持つものの一つである。この数十年、私は「競争」と「価値の創造」の研究に没頭してきた。競争は至るところに存在する。市場で事業を営む企業も、グローバリゼーションに対応しようとする国も、人々のニーズに応えようとする社会組織も、すべて何らかの競争を行っている。そして、すべての組織は、競争を通して顧客に優れた価値を提供するための戦略を必要としている。
そのことは、あらゆる領域で競争が激しくなっている今日、これまで以上に真実である。競争は地理的に広がっており、どの国もさらに繁栄するために──いや、現状を維持するためにも──競争しなければならない。競争は社会のあらゆる分野に広がっている。芸術、教育、保健医療、フィランソロピー(社会貢献活動)など、ニーズの大きさに対して資源が足りないような領域においても競争がある。
今日、あらゆる次元のすべての組織が、価値を提供するために競争しなければならない。「価値」とは、顧客のニーズ(もしくはニーズ以上のもの)を効率的に満たす能力のことである。企業は顧客に価値を提供しなければならない。国は事業を行う企業に立地の価値を提供しなければならない。医療活動を行う病院も、寄付を行う財団も、その点では、製品やサービスを提供する企業と何ら違いはない。何らかの形で社会をよくしようとするすべての組織にとって、少しでも大きい社会的価値──支出一ドル当たりの社会的メリット──を提供することは喫緊の責務なのである。
競争と価値創造を理解するために、私は現実の世界で起きている事象の複雑さをとらえることを目指している。経済学を学び、経済学的推論を身につけた私は、理論を発展させて実務に使えるようにするよう追究を続けている。私のゴールは、理論と実践を効果的につなぐ、厳密で役に立つフレームワークを開発することである。
この本には、競争と価値創造を理解するために私が開発したコンセプトとツールのすべてが収められている。新しい研究成果と、その基礎となった研究の両方が含まれている。各章は、さまざまなレベルの、さまざまな環境下での競争について考察しているが、そこにはすべてを結び付ける一つの共通のフレームワークが存在する。
本書『[新版]競争戦略論』の構成について
本書『[新版]競争戦略論Ⅰ』と『[新版]競争戦略論Ⅱ』は五部構成となっている。第1部「競争と戦略」(邦訳Ⅰ巻・第1部)では、企業にとっての競争戦略の中心的概念を、まず単一の業界レベルで論じ、次に複数の事業を行う企業や多角化した企業のレベルで論じた。競争戦略の中心にあるのは、業界の競争のドライバーは何か、どうすれば企業は競争優位を獲得し維持できるか、どうすれば明確な戦略を開発できるか、という問いである。
特定の事業で競争力を保つ方法を理解できれば、それが企業としてさまざまな選択を行う際の基礎となる。多角化の選択においても、個々の事業の競争と切り離して考えたのでは賢明な決断はできないからである。第1部で論じる原則は、営利企業にとってだけでなく非営利組織にも当てはまる。
『[新版]競争戦略論Ⅱ』に掲載されている第2部「立地の競争優位」(邦訳Ⅱ巻・第1部)では、立地が競争において果たす役割について考える。競争が広がり、激化するにつれ、国、州、そして都市の競争力についての関心が急速に高まっている。テクノロジーによって企業の活動がグローバル化し、資本が国境を超えて自由に移動するようになるに従い、多くの理論家が立地の重要性は低下すると論じている。だが私は、第2部の各章でその考えに挑戦する。
私は、企業と国の繁栄が、競争が行われている地域の環境に依存していることを示した。伝統的には、地域や国の競争力は、主に投資と雇用創出を促す政府の管轄事項と見なされていた。しかし、本書『[新版]競争戦略論Ⅱ』が提示する新しいモデルによって、競争の環境を形成するうえで企業が果たすべき、これまで馴染みの薄かった役割を明らかにすることができた。企業、政府、他の地元諸機関との間に必要となる新しいタイプの関係について、あるいは政府が採用すべき新しい考え方の政策なども明らかになった。
競争における立地の影響を理解することは、第1部の考察とともに、企業がグローバル戦略を設定するうえで不可欠な条件である。
本書『[新版]競争戦略論Ⅱ』に掲載されている第3部「競争によって社会問題を解決する」(邦訳Ⅱ巻・第2部)では、第1部と第2部のフレームワークを利用して、社会に存在するさまざまな課題の解決に迫った。環境汚染、都市の貧困と所得格差、不十分な医療などは社会問題と位置付けられるが、どれも経済学と密接に結び付いている。わかりやすく言えば、競争の影響下にある。
私は最近、これらの問題を自力で永続的に解決できるかどうかは、競争から学んだ教訓を効果的に適用できるかどうかで決まる、という確信を深めている。環境問題やコミュニティの貧困、適切な医療にあずかれない人々の問題などに理にかなった方法で取り組むなら、社会と企業の双方に大きな利益がもたらされる機会が生まれるはずだ。
『[新版]競争戦略論Ⅰ』に掲載されている第4部「戦略・フィランソロピー・企業の社会的責任」(邦訳Ⅰ巻・第2部)では、社会的組織と営利企業の両方に対し、戦略の原則を踏まえた社会貢献事業や寄付・助成のあり方を論じた。今日、社会的ニーズが増す一方で公的財源は乏しい。真の価値を提供する社会貢献事業が強く求められているゆえんである。
さまざまな助成に使われる莫大なお金は、その多くが市民の税金でまかなわれているのだから、社会セクターはその支出を正当化できなければならない。もはや社会貢献活動を支援している、ということだけで支出を正当化できる時代ではない。助成や寄付は社会に真の価値をもたらすものでなければならないのである。
企業部門はかつてないほど社会問題への取り組みを求められており、それはしばしば企業の社会的責任(CSR)というラベルを貼って実施されている。どの社会問題を対象とすべきか、どのように取り組むべきか、助成や寄付はどのように行うべきか──これらは、すべての企業リーダーが結論を出すべき緊急の問題である。
これらの問題を正しく扱うためのカギは、社会問題と経済問題は、相互に排他的な、あちら立てればこちら立たずの関係ではなく、第3部で強調されているように、相互に補完し合う関係にあることを理解することだ。社会の課題に向き合うことは企業の戦略の一部であって、事業と切り離された別の問題ではないのである。
『[新版]競争戦略論Ⅰ』に掲載されている第5部「戦略とリーダーシップ」(邦訳Ⅰ巻・第3部)では、優れた価値創造を実現するためにはリーダーシップが必要であることを論じた。あらゆる組織において、戦略の策定はリーダーの仕事であり、戦略は組織の全員を共通の目的と方向に向かわせるために利用できる最強のツールである。
リーダーシップと同じくらい重要なのがリーダーの役割だが、我々はそれについて驚くほど何も知らない。フォーチュン100とか500といった大きく複雑な組織のリーダーについては、特にそのことが当てはまる。そのような組織では、一人のリーダーがすべての事業を完全に理解するには大きすぎるし複雑すぎる。何千人もの従業員の管理などできないし、全決定のごく一部さえ下せないのが現実である。このような組織では、リーダーの役割は微妙で間接的なものとなる。我々は近年、このようなリーダーの役割についての研究に着手している。
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]競争戦略論の第一人者マイケル E. ポーター(ハーバード・ビジネス・スクール教授)の「競争戦略論」の改訂増補新版。競争戦略、競争優位の戦略、企業戦略のエッセンスがこの1冊でわかる。経営者、ビジネスマン、経営学者の必読書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]先進国産業や企業の成功要因を徹底分析した新立地・集積理論「クラスター理論」や都市問題の解決策を論じるなど、競争戦略の可能性を広げる話題の論文集。国の競争優位、環境対応、都市問題、医療システム競争など企業の競争戦略を鳥瞰して再構築するための理論書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※本書は1998年発行の『競争戦略論Ⅰ』(原著はOn Competition first edition, 1998)の改訂新版です。原著がOn Competition Updated and Expanded, 2008として、first editionから3本の論文を削除して5本の論文を加え、さらに2本の論文を改訂したのに伴い、翻訳書の増補改訂新版としてⅠとⅡとに二分冊して発行しています。Ⅰでは、第1章が改訂、第4章と第6~9章が原著で加わった増補論文です。

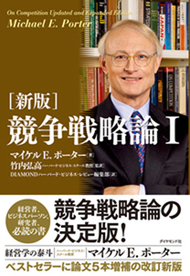





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









