
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
戦略、フィランソロピー、企業の社会的責任
社会問題に取り組むために、社会はすでに政府のみに依存することをやめている。今日では、財団や企業や無数のNGO(非政府組織)が関わるフィランソロピーが、しばしば政府と協力して、難しい社会問題を解決すべく何百億ドルもの資金を投入している。それだけに、稀少資源をこれほど大量に投入してどれほどの価値が生み出されているのかが懸念されてもいる。
『[新版]競争戦略論Ⅰ』に掲載されている第4部(邦訳Ⅰ巻・第2部)では、フィランソロピーによっていかに価値を創造するかという問題をまず論じた。フィランソロピーの大半は、当然よい効果を上げるはずだという前提で助成や寄付といった贈与に向けられている。しかし、第12章「フィランソロピーの新しい課題」(邦訳Ⅰ巻・第6章)で、マーク・クラマーと私は、多くの社会貢献を意図した寄付の多くが、本来可能なはずの効果を上げず、限られた社会的メリットしかもたらしていないという主張を行った。慈善事業家、特に財団が支出する巨額な資金は、社会的な機会損失を拡大させている。
この論考は、財団はただお金を出すだけではわずかな価値しか創造しないと主張して議論を呼んだ。真に価値を創造するためには、財団は助成金を出すだけでなく、意識的な戦略が必要である。この章は、財団が助成を通じて価値を提供する方法を見つけるためのフレームワークを提供している。どのような支援を行えば助成先の社会的インパクトが増大するか、どのような体系的投資を行えば財団が専門性を有する分野での取り組みが進むかを考える必要がある。財団には、活動分野を決める時に、あるいは社会的インパクトをもたらす触媒的役割を果たす活動を選ぶ際に、明確な戦略に基づいた選択を行うことが求められている。
本書第13章「競争優位のフィランソロピー」(邦訳Ⅰ巻・第7章)では、フィランソロピーの一般原則を企業による助成や寄付に適用した。企業は他のほとんどの機関よりも、社会問題への取り組みにおいて価値を生み出せる強力な資産を持っている。しかし、企業が社会的価値を創造する能力は、自社のビジネスに明確なつながりがある社会問題を選び、持てるスキルや資源や関係をそこに投入する場合にのみ発揮することができる。この章では、社会的パフォーマンスを改善すると同時に、長期的な事業の競争コンテキストを強化するウイン・ウインの機会がある分野を見つけ、助成や寄付をより戦略的に行うために使えるツールを提供する。
本書第14章「戦略と社会問題──競争優位とCSR」(邦訳Ⅰ巻・第8章)では、企業と社会の関係に関する広範な問題を論じた。企業はかつてないほどその社会的影響を精査され、説明責任を問われている。だが、多くの企業はCSRには防衛的な姿勢で取り組み、自社が実際に社会に及ぼす影響よりもイメージのことを心配している。しかし、企業の競争力と社会の進歩は、前述のように、別々のものでも相反するものでもない。この章は、企業と地域社会が交わる領域を解説し、社会的責任への取り組みと戦略を統合するためのフレームワークを提供する。社会的側面を戦略に統合することによって、多くの企業は戦略をより持続可能なものにすることができる。
第3部と第4部の各章は、全体として、戦略の原則は経済の発展にとってだけでなく、社会の発展にとっても基礎的条件となっていることを示している。社会にもたらされる価値という観点から考えると、社会に本当の違いをもたらす企業と、価値ある取り組みにただお金を出しているだけの企業はまったく別物であることがわかる。
戦略とリーダーシップ
『[新版]競争戦略論Ⅰ』に掲載されている第5部は、リーダーシップの役割に関する新たな研究を紹介する。企業、国、社会組織は、効果的なリーダーシップがなければ最大の価値を創出することはできない。しかし、私たちはこの微妙な問題についてほとんど知らないことが多い。特に大きく複雑な組織のリーダーシップについてはそのことがいえる。
本書第15章「新任CEOを驚かせる七つの事実」(邦訳Ⅰ巻・第9章)で、ニティン・ノーリア、ジェイ・ローシュと私は、CEOの役割が他のシニアマネジャーとどう異なるかを見ることで、複雑な企業組織におけるリーダーシップの根底にある性質を検証した。この章は、「ハーバード新任CEOワークショップ」で得られたユニークな視点を活かして執筆された。同ワークショップは、新たに任命されたCEOが課題を設定し、変化に対応するのを助けるための集中プログラムである。これまでに、数十億ドル規模の企業から100人以上の新CEOが参加している。
この章は、新人CEOを驚かせる仕事の実態と、その驚きを通して得られるCEOのための教訓を紹介している。これを読めば、CEOとして成功するために戦略が特に重要なツールであることがわかる。この章は、現在も継続中のCEOを対象とする一連のリーダーシップ研究から生まれた最初の論文である。
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]競争戦略論の第一人者マイケル E. ポーター(ハーバード・ビジネス・スクール教授)の「競争戦略論」の改訂増補新版。競争戦略、競争優位の戦略、企業戦略のエッセンスがこの1冊でわかる。経営者、ビジネスマン、経営学者の必読書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
[著者]マイケル E. ポーター
[監訳]竹内弘高
[翻訳]DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー編集部
[内容紹介]先進国産業や企業の成功要因を徹底分析した新立地・集積理論「クラスター理論」や都市問題の解決策を論じるなど、競争戦略の可能性を広げる話題の論文集。国の競争優位、環境対応、都市問題、医療システム競争など企業の競争戦略を鳥瞰して再構築するための理論書!
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※本書は1998年発行の『競争戦略論Ⅰ』(原著はOn Competition first edition, 1998)の改訂新版です。原著がOn Competition Updated and Expanded, 2008として、first editionから3本の論文を削除して5本の論文を加え、さらに2本の論文を改訂したのに伴い、翻訳書の増補改訂新版としてⅠとⅡとに二分冊して発行しています。Ⅰでは、第1章が改訂、第4章と第6~9章が原著で加わった増補論文です。

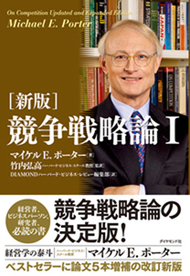





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









