
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
職場に生じる「モヤモヤ」の正体とは?
まず、あるマネジャーの物語から始めましょう。これはフィクションですが、著者が日頃見聞きするマネジャーにありがちな経験を、一人のストーリーとして集約したものです。
「人材開発」とは異なる、「組織開発」というアプローチ
これは若いリーダーを主人公にした架空のストーリーですが、「なんだかうまくいかず、モヤモヤする」というこの感じ、みなさんもおわかりいただけるのではないでしょうか。
思い悩む佐藤さんはリーダーとしての経験が浅い、と感じた方もいるかもしれません。
リーダーとしてまだ2年目の佐藤さんは、これから経験を積めば、きっとうまくマネジメントできるようになるでしょう。また、研修を受けることでマネジメント手法を身につけることもできるはずです。これらは、いわゆる「人材開発」の領域の話になります。
ただ、経験と研修によって佐藤さんがスキルアップするには、少し時間がかかりそうです。モヤモヤをただちに解消することは難しいと言えるでしょう。
そしてもう一つ、このモヤモヤは佐藤さんが一人で抱え、解決しなければならないのでしょうか?いくら佐藤さんがチームリーダーだからといって、それは酷な気がします。
組織のモヤモヤの原因は「目に見えない」ことが多い
この事例において、佐藤さんが率いるチームは、どのような課題を抱えているのでしょうか?また、どうすれば課題が解決するのでしょうか?
佐藤さんの事例での課題は、次のように推移していきました。
①メンバーの一人が休みがちになった
②売上実績が徐々に下がり始めた
③メンバーが密かに不満を漏らすようになった
④業績悪化が明らかになった
⑤リーダー格の若手が転職
「売上実績が徐々に下がり始めた」という事態に対して、たとえば佐藤さんがメンバーに発破をかけたとしたら、業績は回復するでしょうか?根本的な原因が解決されていないため、おそらく難しいでしょう。
売上実績が下がり始めた原因を佐藤さんが分析し、その改善策を考えるにも限界があるように思われます。仮にその改善策が良かったとしても、それがメンバーの「やる気」まで回復させるかどうかはわかりません。
メンバーの一人が休みがちになったという問題についても、体調の問題なのか気持ちの問題なのかは当の本人にしかわかりません。いくら佐藤さんがマネジメントを頑張ったとしても、どうにもしがたい印象があります。
この状況で必要なのは、「目に見えにくいことの調整」 だと言えます。
業績低迷とメンバーのやる気低下は、別個に検討すべき課題であるように思われますが、その2つはおそらく無関係ではありません。同じ要因に根ざしている可能性もあり、それは表面上ではとらえきれない要因である可能性もあるのです。
つまり、一人ひとりの仕事に対する思いであるとか、「もっとこうしたら良いのでは?」というようなアイデアなど、なかなか表に出てこないところにモヤモヤの本当の原因があるのかもしれません。
そこで「組織開発」という手法が浮上します。個人のスキルを向上させる「人材開発」とは別に、組織そのものに着目して「良い組織」を目指して実施するのが組織開発です。
組織開発では、「目に見えにくいこと」をテーブルの上に載せ、みんなで話し合って問題解決を図ります。
[著者]早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫
[監修・解説]中村和彦
[内容紹介]どんどん人が辞めていく、社員にモチベーションがない、などのモヤモヤを、対話のチカラで解消していくのが「組織開発」。本書では、悩みを抱える職場への処方箋として、「組織開発」のはじめ方を成功事例とともに紹介します。組織開発の第一人者と、プロフェッショナル3名によるいちばんやさしい組織開発の入門書です。
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

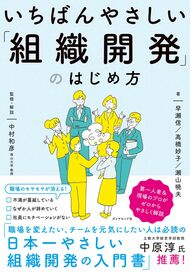




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









