
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「組織開発」とは何か?
ここで「組織開発」とは何かについて、より深く考えてみましょう。
ここ数年、組織開発は、企業のあいだで関心が高まり、実践例も増えてきました。ただ、どうすれば組織開発がうまくワークし、組織が変わるのか、戸惑い、迷っている方も多いように思います。
「組織」を「開発」する、というシンプルな二語からなる言葉ですが、そのシンプルさが逆にわかりづらさにつながっている印象もあります。
いったい、「組織を開発する」というのは、どのような行動を指すのでしょうか。
組織開発は、もともと米国で発祥し、長年にわたって取り組まれ、洗練されてきたものです。その定義は実にさまざまですが、よく知られているものの一つに、次のような定義があります。
(Warrick, D. D. (2005). Organization development form the view of the experts. In W. J. Rothwell & Roland L. Sullivan (Eds.) Practicing organization development: A guide for consultants. 2nd edit. San Francisco, CA: Pfeiffer. pp. 164-187.)
やや硬い表現ですが、組織の 「健全性」 と 「効果性」 というのは大事なキーワードです。本書でも、このあと、何度も使う言葉です。本書の監修者である中村和彦さんの著書『入門 組織開発』(光文社)には、次のような一文があります。
当事者が、自分たちで組織を良くしていくために行うのが組織開発。ぐっとわかりやすくなりました。私たち3人の著者が合意しているのは、次の定義です。
組織開発とは、現場にいる人たちが自ら、人と人との関係性を通して組織内の違和感のあるプロセスを見直し、より良い組織をつくる活動、と言えます。
自分たちが感じるモヤモヤを、自分たちのために修正する。そんな良い組織をつくる活動を通して関係性も豊かになり、組織の健全性も高まると言われています。
組織を良くするために解決すべき課題や、その手法はさまざまです。それがどのようなものであるにせよ、出発点は「何を目的とする組織なのか」を正しく見きわめることになります。これは、誰かが教えてくれることではありません。また、中期経営計画のように、上から降りてくる方針でもないのです。
つまり、自分たちで見定めることが大事なポイントで、そのために話し合いを重ねる。それが、何よりまず実行しなければならないことです。
組織開発で得られる「3つの効果」とは?
では「良いチームや良い組織」の「良い」とは、どのような状態を指すのでしょうか。それには3つの観点があると言えます。
①【効果性】目標達成ができる
企業組織であれば、「予算を達成する」「ヒット商品を開発する」「品質を安定させる」などが想定できます。スポーツチームであれば「試合に勝つ」ことでしょう。つまり、組織として成果を上げられるかどうか、「効果性」という観点です。組織開発では、関係する人々が共に活動するため、納得して目標に向かって動くチームができていきます。その結果、目標達成に素早く近づけるようになるのです。
②【健全性】明るくイキイキ元気がある
目標達成ができる組織の共通点は、「コミュニケーションがきちんと取れている」「助け合える」「教え合っている」など、明るくイキイキしていることです。つまり、組織が「健全性」を保てているか、という観点です。組織開発では、人と人との関係性を築きながら組織のプロセスを見直していくので、人間関係が深まり、支援関係が生まれるためメンバーは元気になっていきます。
③【継続性】良い状態を自分たちで継続できる
目標を達成し、明るく元気がある。でも、人事異動で課長が替わったら、チームの雰囲気が変わり、以前ほど活気がなくなってしまった。結果として、業績も振るわない……。これでは困りますね。
企業に限らず、組織での行動は長く続いていくべきものです。たとえリーダーが替わっても、あるいは先輩が卒業しても、新しいメンバーが入ってきても、同じように明るくイキイキした雰囲気を変えず、目標を達成し続けていく。つまり、組織の風土をつくり上げ、それを維持していく「継続性」という観点です。メンバーの入れ替わりがあったとしても、自分たちに合った組織プロセスをつくり、残った人で継承できることが理想です。必要に応じて再び組織開発を行うことで、良い改善を続けられるようになります。
これら3つの条件を満たし、「良いチームや良い組織」であり続けるために、組織開発は効果を発揮します。
また、その時々の外的な条件や、メンバーのメンタル状態などを要因として、3つのどれかが欠けてしまったり、レベルが下がってしまったりすることもあります。人の健康状態に好不調があるように、チームや組織にもそれが起こります。目標達成ができなかった。元気のないメンバーがいる。そんなときに、話し合いによって本来ありたい状態と現状のどこに差があるのかを見つけ、回復の手立てを考える。それも組織開発の大事な役割になります。
[著者]早瀬信、高橋妙子、瀬山暁夫
[監修・解説]中村和彦
[内容紹介]どんどん人が辞めていく、社員にモチベーションがない、などのモヤモヤを、対話のチカラで解消していくのが「組織開発」。本書では、悩みを抱える職場への処方箋として、「組織開発」のはじめ方を成功事例とともに紹介します。組織開発の第一人者と、プロフェッショナル3名によるいちばんやさしい組織開発の入門書です。
<お買い求めはこちら>
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]

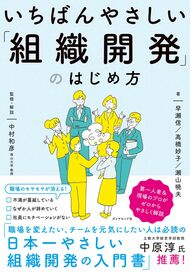




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









