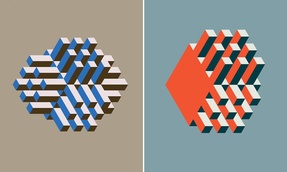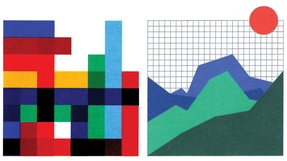-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
戦略の視覚化を効果的に実践しているか
2014年12月1日、サイプレス・セミコンダクターは同業の半導体メーカー、スパンションを16億ドルで買収すると発表した。当時のCEOサーマン・ロジャースがこの買収を公表すると、株式市場は好意的に受け止めた。ある分析によれば、他の交絡因子を除外して考えた場合、サイプレスの株価は買収発表後に13%も跳ね上がったという。同社がこの買収を決めた理論的根拠に対して、投資家が納得したことは明らかである。
この買収の長期的な効果をしっかりと分析すれば、投資家の好意的な見方には根拠があることが見えてくる。買収から丸1年後の同社の価値を調べると、時価総額は買収前より13%高いままであることがわかった。すなわち、株式市場はこの買収劇がもたらす潜在的価値を正確に予想していたのだ。
これと対照的なのが、サイプレスの件から2年前、2012年12月12日に起きた買収劇だ。製薬会社のザ・メディシンズ・カンパニーは、特定領域に特化した製薬会社のインクライン・セラピューティクスを買収すると発表した。価値創造の点から見れば、この買収劇はサイプレスによるスパンションの買収とよく似たものだったとのちに判明する。買収から1年後、合併会社の時価総額は(買収前と比べて)やはり13%高かったからだ。
しかし、ザ・メディシンズ・カンパニーCEOのクリーブ・ミーンウェルがこの買収を金融市場に公表した時、市場の反応はさえなかった。株価は1.8%しか上がらなかったのである。同社がこの買収を決めた理論的根拠を投資家が理解しなかったのは明らかだ。
これには定型のパターンがあることがわかった。筆者らが2012年から2017年までに米国で起きた大型買収654件を標本として分析したところ、似たような買収にもかかわらず、この種の格差が生じたケースが多数見つかったのだ。買収や合併が起きた際、その企業が買収で生じると見込んだ付加価値を市場が即座に織り込むとは限らない。
では、CEOの言葉を投資家が信じるか信じないか、両者の違いはどこから生まれるのだろうか。その理由を明らかにするため、筆者らはイベントスタディの方法論を用いて、統計学的な分析を行った。ある買収案件(「イベント」に該当)において、市場がどのように反応するかを決めるのは、その買収のいかなる特徴からなのかを分析したのだ。
そして、筆者らが標本とした買収案件を通して、ある一つのシンプルながら重要な要因が浮かび上がった。買収を発表するプレゼンテーションの場で、その買収を行う戦略的な理由をわかりやすく説明する一枚のスライドがあった場合、投資家が即座に賛意を示す確率が2倍以上に上昇するのだ。
筆者らはそのようなスライドのことを「ストラテジー・ビジュアライゼーション」(戦略の視覚化)と呼ぶ。戦略の視覚化が買収発表後の企業価値にもたらすプラスの効果は、写真や地図、ロゴマーク、さらには棒グラフや折れ線グラフといった他の視覚化ツールと比べて4倍だった。