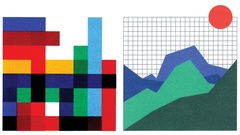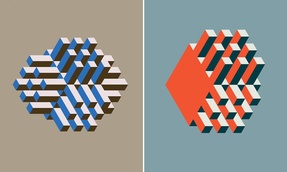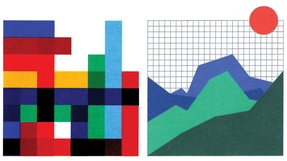-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
なぜ戦略立案は非効率がまかり通っているのか
リーン生産方式が目指すのは、製品を可能な限り安全かつ容易に、また効率的な方法で生産できるよう、明確な手順を確立することである。業務プロセスがこうした「標準作業」になれば、製品のばらつきが減り、時間当たりの生産量(スループット)が高まり、コストが減少し、品質が向上する。トヨタ自動車やアマゾン・ドットコム、インテル、ナイキといった多様な企業がこの手法を事業に活用して大きな成果を挙げている。
これに対して戦略の意思決定は、大半の企業で「非標準作業」の典型となっている。戦略に関する判断は、まるで雪の結晶のように一つひとつ異なり、それぞれに特別のプロセスが必要だと見なされがちである。その結果、たとえば「新たな市場に参入するか否か」といったよくある意思決定が、同じ企業内であってもまったく異なる方法でなされることも多い。
こうした一貫性の欠如が、意思決定のスピードや質の低下を招く。この問題は、ベイン・アンド・カンパニーが350社の大企業の幹部に対して実施した戦略プロセスに関するアンケート調査によって得られた回答にも、はっきりと浮かび上がった。筆者らは調査で以下の点を見出した。
・回答者の50%近くが、自社では戦略計画の立案に標準となる雛型を用いていると答えたが、重大な意思決定において常に同じやり方をしている企業はほとんどなかった。多くの場合、重要な意思決定のプロセスは、責任者である幹部に委ねられているか、意思決定の種類によって異なっていた。
・企業が下した戦略的意思決定の4分の1が、後から振り返ると最善の策ではなかったと、回答者らは答えた。選ばれた戦略は正しくなかったか、他の選択肢に比べて劣っていた場合がよくあった。その多くは変更にかかる費用が高いか変更が不可能で、企業は長期間にわたってその影響を受けることとなった。
・回答者の企業では、45%以上のケースで意思決定が遅すぎた。その結果、最終的に正しい判断を下せた場合であっても、意思決定が遅れている間に市場や競争状況が変化し、成果に影響が出ることが多かった。
・戦略で狙った結果の達成率は、回答者の企業では平均で70%未満だった。こうした場合、戦略自体には問題がなかったとの認識の下、たいていは戦略の実行面での不十分さに責任が帰せられた。しかし実際には、戦略的意思決定の内容そのものが不明確だったために、実行面で調和を欠き、時には矛盾にもつながり、不十分な成果しか生まれなかったケースも多い。あるいは、幹部が意思決定をしたと考えていても、実際には「望ましい結果」を説明しただけで、それを達成するのに必要な行動指針を示していなかった場合もあった。このように、実行すべきことが何一つ固まっていなかったために、満足のいく成果が挙がらなかったのだ。
仮に製造プロセスで、欠陥率が25%に達し、サイクルタイムの超過が45%を超え、歩留まり損失が30%以上であったら、その工程は許容されないだろう。しかし戦略立案においては、このレベルの非効率や効果のなさが多くの企業で容認されているのである。
いまこそ、よりよい結果を実現するために、戦略プロセスを設計し直す時である。重要な製造プロセスと同様に、戦略の意思決定を標準作業にできない理由はない。そのための徹底したアプローチを採用することによって、企業は無駄を減らし、動きを速め、よりよい意思決定を行い、競争力をつけることができるのである。