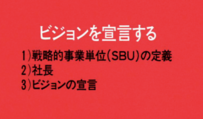-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
構造改革を「構造の改革」としてやろうとすると失敗する、という話をしている(詳しくは前2回を参照)。この手の愚を犯す人に共通しているのは、「構造改革が不可欠だ!」という気持ちがほとばしるあまり、いきなり丸ごと全体を変えようとするということだ。
もちろんさまざまな問題を突き詰めれば今の「構造」に行き当たるわけで、究極的には「構造」を変えなければならない。しかし、だからといって丸ごとすぐに構造全体を変えようとすると、それとこれとは話が違うということになる。構造はその定義からして丸ごとすぐに変えられない性質のものだ。だからこそ、いつまでたっても「構造問題」が問題として解決されないまま残っている。すぐに解決できるような問題であれば、そもそも構造問題などにはならないのである。
構造は改革の直接的な対象とはなり得ない。構造改革はあくまでも結果として認識されるものだ。過去に成功した「構造改革」をみても、振り返ってみたときに「そういえばずいぶん変わったな……」というものが多い。構造改革者は遡及的にしか同定できない。最終的には構造改革を視野(の片隅)に入れているにせよ、構造改革を直接の目的としてアクションを起こすわけではない。彼らがやろうとしているのは、いまそこにある特定の問題を解決し、それによって具体的な成果を出すことの方にある。そのうちの構造全体までを変えてしまう力を持つアクションが事後的に構造改革を引き起こし、新しい構造が現れ、世の中に定着する。ようするに、結果として出現する構造改革者は「構造改革」を待たずに動きだす人々であり、前にも話したように「構造改革に全力で取り組みます」という手合いはあまり信用できない。
丸ごとすぐに構造全体を変えようとする「構造改革者」に共通の性癖は、一撃で構造を変えることができるような(正確にいうと「変える気分になれるような」)「飛び道具」を探して回る、ということだ。いつの時代も「構造改革の決め手」と目される「旬の飛び道具」が現れては消えていく。
すでに旬の時期を過ぎた感がなきにしもあらずだが、十年ぐらい前の「IT!」には、飛び道具中の飛び道具というか、必殺技の王者の風格があった。ITベンダーの甘言に乗って「わが社もITで構造改革!」とばかりに無駄なカネをドブに捨てた会社は少なくない。いまも昔もITが便利で有用で効果的なツールであることは言うまでもない。しかし、だからといってそれが自動的に構造改革をもたらすかというと、構造というのはそんなに甘いものではない。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)