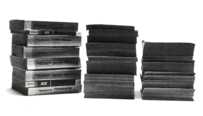-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
競争が過激化すると差別化はより細分化し、結果、消費者から見てほとんど違いが見えなくなる。まるで誰もが没頭しながら、誰も1人勝ちできない「鬼ごっこ」のようだ――。ハーバード・ビジネススクールでいま最も注目を集めるヤンミ・ムン教授の処女作『ビジネスで一番、大切なこと』、無料公開連載、第3回。
ビジネスの成功の要は、競争力にある。競争力とは、競合他社といかに差別化できるかである。ところが、その差が細かくなりすぎて、多くの消費者がいぶかしく思う段階に達すると、ある日突然、差別化は無意味になる。
その1つの兆候は、カテゴリーに対する消費者の愛着が弱まるだけでなく、愛着を示すこと自体が馬鹿馬鹿しく見え始めることだ。カテゴリー通でいるためには、微細な違いにもこだわらなくてはならない。だが、普通の人が気にもかけないところにこだわりすぎると、最初は専門家だと一目置いていた周囲もやがて眉をひそめるようになる。
このように、製品の違いを信じている人が笑い者にされかねない段階を、私は「異質的同質性」と呼んでいる。違いは確かに存在するが、類似性の海に埋もれている。無意味な差別化が進めば進むほど、嘲笑指数は上がっていくのだ。
* * *
「安値で買い、高値で売れ」「汝の敵を知れ」「顧客の声を聞け」。これらはビジネスの大原則として私たちの骨の髄まで染み込んでいる。そのせいか、疑問を投げかけられると、私たちは無意識に防御に回るだけでなく、その意見を否定しようとする。
バスケットボールに24秒ルールが導入されたのは、試合のテンポを上げ、得点を増やすためだ。以後、勝つためには1点でも多くを稼がなくてはならなくなった。だからこそ、1956年、57年のボストン・セルティックスの活躍は、スポーツ史に残る特筆すべき出来事なのである。セルティックスは得点を稼ぐタイプのチームではなかったにもかかわらず、ディフェンスの名人ビル・ラッセルに率いられ、13年間に11回も優勝し、通念を覆した。
当時ほとんどのファンは、ラッセルを例外的な超人だとみなしていた。挑戦者が登場し正統派の地位を脅かすとき、おおかたの最初の反応は例外を例外として扱うことであって、正統派に潜む欠陥を認めることではない。さもありなん。逸脱は、まさに逸脱なのだ。
しかし、逸脱は何かの前触れにもなる。私たちが暗黙のうちに前提としている基盤を揺るがしかねない。今日のバスケットでは、誰もがディフェンスが勝利のカギだと思っているが、いつからそうなったのだろう。例外が頻繁に出現するようになると、もはや例外ではなくなり、既存の原則は変わらざるを得なくなる。最後には、これまで信じていたものがただの神話、つまり誤った集団的信念やイデオロギーの名残だったことが明らかになる。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)