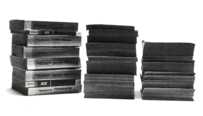トンネルのなかでも外の景色が見える「光学迷彩」
――漫画『攻殻機動隊』に登場する技術「熱光学迷彩」を実際に開発した研究者として世界的に有名ですが、その発想と狙いを教えてください。
そもそも私は立体映像の研究をしていました。立体映像というとメガネ型のデバイスをかけると、テーブルの上にキャラクターが出てきたりするのが典型で、私が手掛けていたのはプロジェクターと再帰性反射材という特殊な素材を使いメガネなしで立体映像を観察可能なシステムで、1997年頃から研究を始めていました。ある時、机の上に、床の模様を奥行きがあるように立体的に映せば、結果的に机が透明になったような効果を生み出すことに気がつきました。
そこで誕生したのが光学迷彩です。ものに投影すれば、あたかも透視しているような気分になれるし、人に投影すれば透明人間に見えます。この技術が世界から注目を集めるのは、人は「消える」ことが好きだからしょう(笑)。
たとえば、自動車で車外の様子が透けて見えるようにすれば死角がなくなります。将来的な応用で最も期待しているのはリニアモーターカーです。ほとんどトンネルのなかを走ることになりますが、光学迷彩の技術を使えば、トンネルのなかでも外の景色が見えるようになります。
――メガネ販売チェーン大手のJINSが開発した「JINS MEME」を使った実験も手掛けています。
このメガネには、目の動きやまばたきの頻度などを計測できる機能がついています。目の動作には「疲労」「集中力」「病気」「眠気」をはじめ、さまざまな情報が入っているので、その情報を分析すれば、たとえば、「バッターのフォームが悪いのは疲れがたまっているから」「ビジネスマンの疲れが抜けないのは、実は睡眠時無呼吸症だった」といったことがわかります。
そこで、スポーツ医学、加齢医学、眼科学などさまざまな研究者が専門の立場から、目の情報を分析するアプリを開発しています。我々は、人間の集中力を計測するアプリを開発しました。英語などを読ませれば、動揺などが一発でわかります。ですから、生徒の前で自分は決してかけません(笑)。今後は、一人暮らしの高齢者の安否を確認できるアプリなどを開発できればと思っています。
このメガネが優れているのは、そうした機能がついているようにはまったく見えない普通のメガネであることです。デートでも、食事でも、かけていて恥ずかしくない。これまでウエアラブル・デバイスは、コンピューターを搭載するという発想が先に立ち、肝心のメガネという機能が置き去りにされていきました。ようやく本物のウエアラブル・デバイスが出てきたという印象です。
――バーチャルリアリティについては、古くから研究に取り組まれています。進展はいかがですか。
私がバーチャルリアリティに興味を持ったのは、1990年、大学一年の頃でした。当時は、とにかく何もかもが高価で限られた人しか体験できませんでした。何しろメガネ型のディスプレイ一つが200万円から400万円、コンピューターグラフィックスを映し出すためのワークステーションは2000万円から1億円もしました。しかも、ワイヤレス通信が不自由な時代でしたから、メガネ型のディスプレイをつけて動けるのはケーブルが届く範囲のみ。その状態を「鎖につながれた犬」と言っていました。
あれから20年で社会や研究環境は大きく変わりしました。まず、インターネットの商用利用が認められ、ワイヤレス通信が発達しました。普通に使っているスマホでも、当時のコンピューターと比べれば、計算速度、通信速度ともに1000倍以上です。GPSも使えます。生物学でいえば、これでようやくイン・ビトロ(試験管)からイン・ビボ(生体)へ、限られた人が実験室でしかできなかったことが、広く一般の人もできるようになったのです。この変化が最も大きいでしょう。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)