-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
「ポケモンGO」が爆発的な人気を集め、ソニー・インタラクティブエンタテインメントなどから、一般消費者向けVR用ヘッドマウントディスプレー(HMD)が低価格で発売されるなど、「元年」ともいわれる今年、仮想現実(VR)を取り巻く環境が大いに沸いている。VR研究の第一人者である東京大学の廣瀬通孝教授にVR技術の進展と、VR研究の未来について語ってもらった。
今年は「VR元年」ではなく、「VR 2.0元年」
――2016年は仮想現実(VR)元年といわれています。長らくVRの研究に携わってきたなかで、VR技術の進展をどうご覧になっていますか。
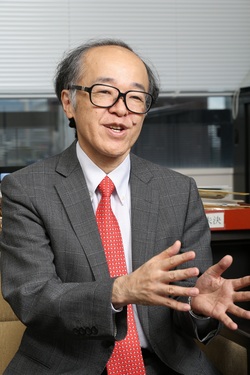
微妙な印象です(笑)。VRという言葉が登場したのは1989年のこと。VPL Research社の創設者ジャロン・ラニアが最初のVRのブームをつくりました。コロンブスのアメリカ大陸発見に匹敵する新たな大陸の発見という意味で、「Virtual Realty(=不動産)」という言葉も生まれたくらいです。当時は、クリントン政権下のアル・ゴア副大統領が情報スーパーハイウェイ構想を言い始めたころです。リアルワールドでは戦争になるようなことも、バーチャルワールドでは無限に解放されているということで、ラニアはVRのことを“欲望のスポンジ”と呼びました。その一部は現在、インターネットが役割を果たしています。
正確に言うと、いまのVRブームは「VR 2.0」です。最初のブームから四半世紀が経って、VR研究を取り巻く周辺環境は大きく変わりました。何よりVRという言葉が浸透し、新たな研究分野として確立されたことは、我々研究者にとっては大きな意味を持ちます。3次元でインタラクティブに動くCGを面白がっている人間が「あなたは何をやっているの?」と問われて、「VRの研究」とひと言でいえるようになったことは隔世の感があります。
VRの技術的コンセプトは、第一世代の頃にほとんどありました。第二世代になって何が大きく変わったのかというと、それはコストです。1989年当時のヘッドマウントディスプレー(HMD)は数百万円もして、しかも解像度が100×150画素でした。その後、米国で軍事用に使われている光学系を積んだハイビジョン(1K)画質のHMDが登場しましたが、2000万円もしました。ところが現在は、オキュラスVR、HTC、ソニーのプレステVRなど、5万~10万円で発売されているわけです。しかも、これらは1Kぐらいの解像度を持ちます。
今回、再びブームが来てよかったなと思うのは、VRの研究者が地道な努力を積み重ねてきた結果、周辺技術も含めて飛躍的な進化を遂げたことです。VRの技術はシステムの技術です。VRとともに、新しい生態系をなす高速のグラフィックエンジンやHMDに映像を供給するカメラ、大容量高速ネットワーク、VRコンテンツのオーサリングツールなどが共進化したと言っても過言ではありません。
――先生ご自身の研究はどのように変化してきましたか。
1980年代の終わりから1990年代の始めにかけて、心理学者と仲良くつき合っていたことがありました。VRと心理学が融合したところにものすごい領域がありそうだということで共同研究を始めたのですが、我々が実験装置を貸すぐらいで、こちらの持ち出しが多く、しばらくすると疎遠になってしまいました。
ところが、2000年ぐらいからVRは「五感の技術」だといわれるようになって、Pseudo-Hapticsなど、触覚をバーチャル化するような技術が登場し、状況は一変しました。それまで触覚のディスプレーというと、ものすごくごつい装置が必要だったのですが、人の錯覚を利用することで、驚くほど低コストでつくれることが可能になり、心理学研究の評価が高くなりました。いま、再び心理学者に接近しているところです(笑)。




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)





