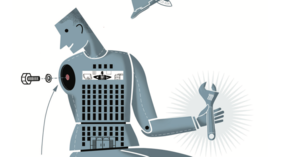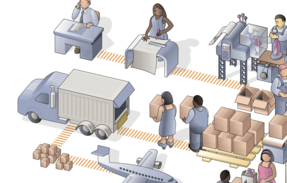-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
戦略の進歩は止まってしまった
戦略は、本来の目的を忘れてしまった。どうしてだろう。
かれこれ25年ほど前から、戦略は分析的な問題解決の方法であり、左脳型の作業として見なされるようになった。このような認識から、また「戦略は金になる」ということから、MBAホルダーや戦略コンサルタントといった一種の専門家が現れた。彼ら彼女らはフレームワークやテクニックで武装し、業界分析や優れた戦略を指南し、経営者のよき参謀となった。
実際、このような考え方によって、いろいろな副産物が生まれた。いまや市場動向が収益性に及ぼす影響やライバルとの差別化の重要性は、だれもが知っている。このような恩恵は経済理論に負うところが大きい。こうして戦略は、より有意義な理論性と経験的妥当性を獲得し、厳密性と実現性が高まった。
しかし、これらはけっして無償の産物ではない。戦略が正当なものとして発展していく過程では、予期せぬことも多かった。特筆すべきは、戦略は大局的(ホリスティック)な目的から遠く離れ、競争ゲームの計画に矮小化されてしまったことである。
その結果、戦略の責任者と監督者というCEOの役割は薄らぎ、また持続的な競争優位ばかりが注目され、戦略が本来、永続的な発展へと企業を導くダイナミックなツールであることは忘れ去られてしまった。
このような認識を改めるには、競争について再考する必要がある。そのためには、競争の本質は流動性にあることを認識しなければならない。そして、一過的ではなく、継続的なリーダーシップが求められる。
半世紀前、戦略は、ビジネススクールにおいて経営管理コースの一科目にすぎなかった。学問の世界でも実学の世界でも、戦略はCEOの最重要任務と認識されていた。CEOは、自社が進むべき方向性を示し、わき道に逸れることなく前進していくことに全責任を負っているからだ。したがって、CEOには、戦略を策定し、これを実践すること、すなわち思索と行動の両方が要求される。
戦略は当時、その対象範囲が広いため、厳密さに欠けていた。元ハーバード・ビジネススクール名誉教授、ケネス・アンドルーズらが開発したSWOT分析[注1]のおかげで、企業内部の「強み」と「弱み」、外部環境における「チャンス」と「脅威」がわかるようになったとはいえ、分析という意味ではありきたりな手法であった。