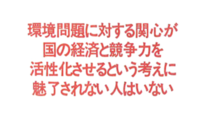-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
企業やNPO、行政などが協働して、地球温暖化や貧困などの社会課題を解決する「コレクティブ・インパクト」。DHBR最新号では、いま世界を動かす注目のアプローチを特集しています。
成功者が社会変革に挑み
企業がCSVを実践する時代
コレクティブ・インパクトという言葉の初出は、2011年にハーバード・ビジネス・スクール(HBS)客員講師のマーク・クラマー氏らが『スタンフォード・ソーシャル・イノベーション・レビュー』で著した論文です。今号ではその歴史的経緯から直近の動向、モデルとなる企業の活動、先端技術の活用法まで、幅広い視点で特集しています。
特集の第1論文は、この分野の第一人者、慶應義塾大学特別招聘准教授の井上英之氏が、「コレクティブ・インパクトとは何か」や「いかに実践していくか」を提示します。ビジネスでの成功者や企業が社会変革に挑むようになった経緯や理由、「私」と仕事と世の中が直結することの意義、日本の役割や日本での実例が理解できます。
第2論文は、前述のクラマー氏が同僚とともに、コレクティブ・インパクトを実現する5つの要素を解説した2016年のHBR論文の要約ですが、ここには発案者なればこその提言があります。彼は先の論文と同時期の2011年に、HBS教授マイケル・ポーター氏と共著で論文「共通価値(CSV)の戦略」をHBRに発表(翻訳はDHBR2011年6月号に掲載)し、企業が社会的価値と経済的価値を同時に創造することの意義を説いたのです。
こうした活動を企業が成功させるのに不可欠なのが、ステークホルダーの理解です。投資家や従業員、地域社会との協調を論じているのが、特集3番目にまとめた3つの短い論文です。1つ目はプロセスを、2つ目は社会へのアピール法を、3つ目はCSVが投資リターンの低下を招かないという実証研究を紹介しています。
そして、大企業におけるコレクティブ・インパクトのモデルになると考えられるのが、第4論文です。世界的金融グループのステート・ストリートの会長が、非営利団体を連携して、社会変革を果たしたプロセスや考え方を明かしています。
社会課題を解決するのに最新技術の活用は有効ですが、技術が革新的であると、社会はその影響力を不安視して容易に受け入れません。第5論文ではその対処策を、先端技術のドローンを活用して途上国で医療品搬送の道を開いた企業事例などから示します。
ポイントは、行政や競合企業などを巻き込み、自社が開発したノウハウなどを利害関係者に活用してもらうことです。関係者の信頼を得て、新しい産業の発展を促すエコシステムを構築し、社会に恩恵を施すことが肝要と論じます。






![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)