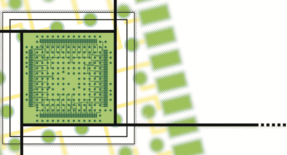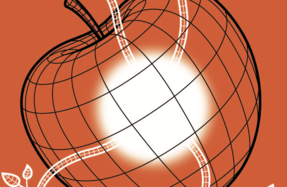-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
デファクト・スタンダードの3つの誤解
不幸は、えてして誤解によって招かれる。これまで数々のビジネス・ジャーゴンが生まれてきたが、その解釈を間違えたり、本質を見誤ったりした結果、そのアイデアの本来意図するところが、なおざりにされてしまったというケースは枚挙に暇がない。
たとえば1970年代、コーポレート・アイデンティティ(CI)という概念が提唱され、日本産業界に一大ブームを巻き起こしたことがある。その背景には、まず国際化があった。当時の日本企業の大半が社名やロゴをまだ日本語で表記しており、これでは海外の市場や企業、投資家たちの認知を得ることが難しい。
また、国際化を推し進めるには、経営者以下、社員たちのマインド・セットや体質を変える必要もあった。当時、大企業の多くで多角化が進んでいたこともあり、必然的に「自分たちは何者なのか」について再定義する、すなわちアイデンティティを再構築することが変革のコンセプトとなった。
ところが、企業の変革プロジェクトだったはずのCIは、概して社名やロゴを変更するだけの作業、たとえばシンボル・マーク、名刺、封筒、便せんなどのリニューアルにとどまってしまった。その結果、CIはビジュアルの変更にすぎないという汚名をいただくはめになった。
ビジネスプロセス・リエンジニアリングも同様である。そもそもは、分業化され、部分最適に陥っていたバリューチェーンの各機能を、ITを用いて再結合を図り、全体最適を実現することが趣旨であり、その副産物としてホワイトカラーの生産性が改善するというものだった。いま考えてみれば、何とも壮大なチャレンジであった。
ところが日本では、継続的改善の延長、あるいはリストラクチャリング(この言葉も誤解された典型例の一つである)の同工異曲と位置づけられ、みごと曲解されてしまった。結局、大半の企業が、組織改編、職務職掌の変更など、小手先の改革に終始した。
そしてもう一つ、さまざまに誤解されている言葉がある。「デファクト・スタンダード」(de facto standard:事実上の標準)である。この言葉が日本で使われ始めたのは90年代前半からだが、拡大解釈されたり、誤解されたりすることが多い。たとえば、このような発言を耳にされたことがあるのではなかろうか。
「英語はビジネスの世界標準語となり、まさしくデファクト・スタンダードの典型例である」
「世界中の消費者の舌が知っている〈コカ・コーラ〉は、数あるコーラ飲料のなかで、押しも押されもせぬデファクト・スタンダードである」
「全世界の、しかもあらゆるスポーツ競技の選手たちが履いており、圧倒的なシェアを持つナイキのシューズは、いまやデファクト・スタンダードとなった」