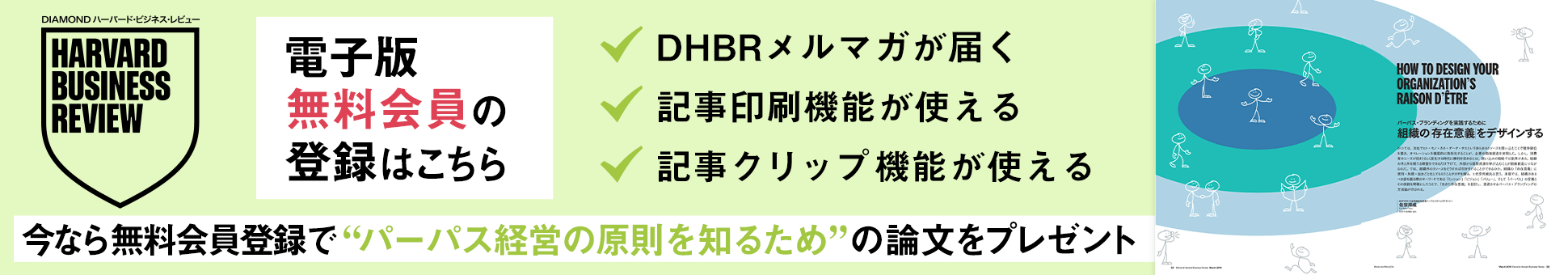たいていの企業にとって、人事部門の問題は、データを使うことがそもそも難しい点にある。なぜなら、採用や業績管理など業務別のデータは、異なるデータベースに存在することが多いからだ。
別々に格納されているデータに互換性を持たせない限り、応募者のどの特性を見れば優秀な人材を見つけられるかという、最も基本的な質問すらできない。換言すると、ほとんどの企業には(大企業も含めて)立派なデータサイエンティストは不要なのだ。
必要なのは、データを整えるデータベース・マネジャーである。さらに必要なのは、簡単なソフトウエアだ。たいていの人事部門で必要な分析は、しばしばエクセルでこなせてしまう。
人事分析のもう1つの大きな特徴は、本当に重要な問題が、他のどのビジネス課題よりも、長期間にわたってすでに研究されてきたということだ。
たとえば、成功する採用の条件については、第1次世界大戦以降、同じような研究がなされてきた。そのため、人事データを分析するために、機械学習による探索的データ分析技術を取り入れたところで、これまで知られていなかった深い洞察を得られる可能性は限りなくゼロに近いだろう。
グーグルの非常に有名な取り組みを見てみよう。
同社は何年もの間、優れたマネジャーの条件を解き明かすべく設計された複数年調査、「プロジェクト・オキシジェン(Project Oxygen)」のような取り組みによって従業員のデータを分析してきた。他のどの企業もなしえなかった、しっかりとした調査だった。しかし、きわめて充実したこの調査で得られた結論は、何十年も前の調査で発見されたものと大して変わりなく、教科書に出てくるような内容だった。
こうした標準的なマネジメント仮説が自分たちの組織でどのように展開するか試してみることには、それなりの価値がある。ただ、深くて斬新な洞察が得られると期待するのは、見当違いだということだ。
人事データはその性質上、分析時に特有の制約を課せられる。
たとえば、EU圏内で事業を展開する企業は、国境を越えて合法かつ容易には従業員データを動かせないことを知っている。多国籍企業は、国をまたいで従業員データを合法的に同時検証することができないのだ。米国では、従業員データの分析で保護対象グループに不利益となる可能性(たとえば、ある部署の女性従業員は男性従業員より賃金が低いなど)が明らかになれば、他のビジネス部門では起こらないような法的、さらには経営的対応が必要となる。
人事部門は、こうした制約を理解していない部署には人事データを安易に渡さないように、気を付けなければならない。