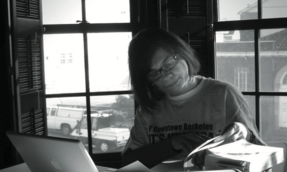-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
なぜイノベーションを生み出せないのか
「専門バカ」という言葉がある。文字どおり、ある分野の知識や能力は抜群だが、それ以外のことにはからきし無知・無関心なことである。ただし裏返せば、一つの道を究めることに一生懸命であり、少なくとも一芸には秀でているといえる。
そこには、スペシャリストへの賛辞と皮肉が込められているが、企業組織、特に大企業というものは──むろん個々の能力にばらつきはあるが──おしなべて「専門バカの集団」といえるのではなかろうか。
製造のプロ、技術のプロ、品質管理のプロ、マーケティングのプロ、営業のプロ、サービスのプロ、人事のプロ、財務のプロなど、ある分野に詳しい人たちが集まることで、事業は営まれている。彼ら彼女らはみな勤勉であり、自分の仕事に誇りを持っている。
たいていの企業が、これら企業活動を支える主要機能に、もれなく優秀な人材を配置している。ところが、個の総和以上の価値、要するに「シナジー」や「イノベーション」を生み出せずにいる。
この問題は古くて新しい。これまで、さまざまなアイデアや試みがなされてきた。たとえば、かつて「T字型人間」というモデルが奨励されたことがある。自分の専門分野を深めつつ(Tの縦棒)、専門以外の分野についても見聞を広めることで(Tの横棒)、他部門との協調が促されるというもので、もちろん悪いことではないが、シナジーを生み出すまでには至らなかった。
進化は、これまでの均衡が崩れることで生じるといわれる。そこで、同質的な組織にゆらぎを起こし、不安定な状態にすれば、イノベーションが生まれてくるだろうという考えから、社内のマージナル・マン(辺境人)といった異質の力を活用するといったアイデアもあった。しかし、異質を拒む壁は厚く、またいきなりそのような大役を仰せつかったマージナル・マンたちには心の準備も能力の準備もなかった。
新しいところでは、カルロス・ゴーンが1999年10月、「日産リバイバル・プラン」の発表と合わせて導入した「クロス・ファンクショナル・チーム」が、その一つの処方箋として持てはやされた。
各部門の代表者が鳩首集まり、さまざまな視点を持ち寄り、文殊の知恵をひねり出そうという試みだが、実はけっして簡単ではない。概して、それぞれの利害を調整することに終始しがちで、シナジーなどとうてい望むべくもなく、やがては疲れ、尻すぼみになっていく。
また、オープン・イノベーション、バリュー・ネットワーク、イノベーション・エコシステムなど、さまざまな言い方があるが、NIH(not invented here)症候群、すなわち自社開発だけを是とする閉鎖的な態度を乗り越え、積極的に外部の力──時にはライバルでも──を活用するというアプローチが広がっている。ソース・コードをオープン化した〈リナックス〉、だれでもその編集に参加できる〈ウィキペディア〉などが有名である。
たとえば、現在プロクター・アンド・ギャンブル(P&G)では、2000年にダーク・イェーガーの後を襲ったアラン G. ラフリーの下、「コネクト・アンド・ディベロップ」というR&D活動が進められている。