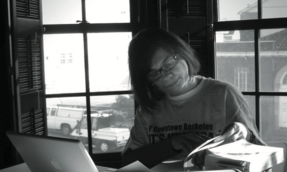-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
なぜ否定的な情報が隠ぺいされたのか
数十億ドル企業のトップが何年か前に、ある製品(ここでは「製品X」とする)に見切りをつけて、市場から撤退すべきであるという判断に至った。この製品に関わる損失は1億ドルを超えていた。
ところが、生産中止が決まる6年も前に、少なくとも5人の関係者が、この製品には深刻な問題があることに気づいていたという。そのうちの3人は工場主任として、日々生産上のトラブルに遭遇していた。ほかの2人はマーケティング担当で、生産上のトラブルを解決するためには多額の支出を要し、それを価格に転嫁すれば、市場競争力を失いかねないと見ていた。
このような情報は上層部に伝わるまでに時間がかかったが、それにはいくつかの理由がある。
第1に、現場の人たちは、自分たちが粉骨砕身すれば、問題を克服し、成功できるに違いないと思っていた。ところが、骨を折れば折るほど、大元の問題がいかに大きいかに気づかされるのだった。
そこで彼らは、悪い情報を社内に伝え広めようとした。この企業では、悪い知らせは改善提案を添えない限り歓迎されず、それについては当事者たちも心得ていた。経営陣が製品Xを「市場における次の主役」と熱心に喧伝していることも承知していた。このため、経営陣にがっかりさせないように気を遣いながらも、現状を伝えるための資料を長い時間を費やして作成した。
その資料に目を通したミドル・マネジャーたちは、「あからさますぎる」と感じた。製品Xの生産に踏み切るに当たって、会社は生産とマーケティングについて分析していたが、現場から上がってきたこの資料は、その分析の中身に疑問を投げかけるものだった。
そこで、ミドル・マネジャーたちは時間稼ぎに出た。資料に記された悲観的な予測が本当に正しいのか詳しく調べ、もし正しいと判明したならば、改善策について検討しようというわけである。悲観的な情報を上層部に伝えるならば、それを緩和するような明るい材料として、改善策を添えたかったのだ。こうして上申はさらに遅れた。
やがて、最初の資料にあった悲観的な予測が正しかったことがわかり、ミドル・マネジャーたちは都合の悪い情報を明かし始めたが、あくまでも小出しだった。仮に経営陣が怒っても、自分たちに火の粉がふりかからないように慎重に行動した。
具体的には、資料の中身を大幅に割愛し、結論を要約したのである。その理屈は「いつも上から『資料が長すぎる』とお叱りを受けている」というものだった。
かくして、経営陣の下には断片的な情報しか届かなかった。しかも、問題の深刻さに関する記述はオブラートで包まれ(深刻さそのものは変わっていない)、ミドル・マネジャーと技術陣が実際以上に事態を把握しているかのように表現されていた。