
Colormos/Getty Images
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
メンタルヘルスが悪化し、希死念慮を抱いたり、自殺を図ったりするリスクを抱える人が増えている。みずから命を絶つ行為は、個人の属性や環境条件、自殺手段へのアクセスを含めて、さまざまな生活要因の影響を受ける複雑な現象だ。しかし、職場体験が自殺行動に関連する事実を考えれば、組織には従業員の自殺予防に取り組む義務がある。本稿では、自殺の職場要因について解説したうえで、組織が講じるべき3つの措置を紹介する。また、同僚を自殺で亡くした場合に、遺された従業員をサポートするための事後対応についても論じる。
1999年から2018年までの間に、米国における自殺率は35%上昇した。毎年約4万7000人、1日で約130人がみずから命を断った計算になる。その大部分は、生産年齢にある人だ。統計によれば、職場で自殺を図る人も記録的な数に上る。
世界中でコロナ禍との戦いが続く中、メンタルヘルスが悪化したり、自殺を考えたり、自殺を図ったりするリスクを抱える人がますます増えている。組織が自殺予防に果たせる役割をこれまで以上に認識し、自殺を考えている人を支援することが、これまで以上に重要になった。加えて、同僚が自殺で亡くなった場合に、遺された従業員をサポートするための戦略を練ることが、組織に強く求められているのだ。
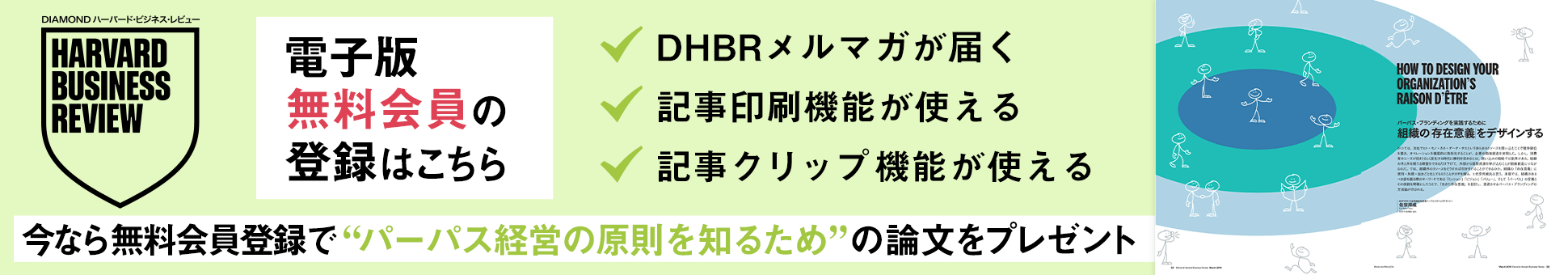




![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









