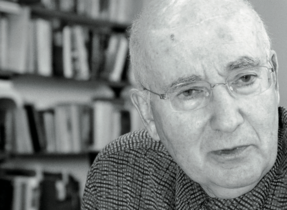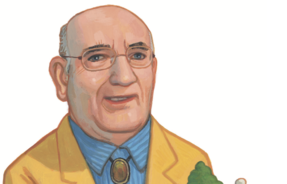-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
顧客志向のマーケティングは部門間の連携を求める
マーケティング志向を徹底することで、自社の存在意義、目標とその達成について考える。これはいまや当然のことだ。「マーケティング・コンセプト」とは、モノ余りの経済環境において、ビジネスを効果的に展開するための原理である。
この10年間、大半の企業は、自社の供給能力に見合うだけの顧客をいかに獲得するかという問題に腐心してきた。その問題を解決するカギは、顧客ニーズをよりていねいに観察し、よりきめ細やかに対応することと考える企業が増えている。
このような新たなマーケティング・コンセプトが、いかなる商品であろうと、これを売り込むのがマーケティングの仕事であるという既存のコンセプトに代わろうとしている。
これは、これまでの論理を逆転させて「売れる商品をつくる」ことを迫るものだ。すなわち、満たされていない顧客ニーズを発見し、ウオンツを充足させることで、利益を追求し、顧客に何らかの影響力を及ぼすために、社内のあらゆる職能を連携させることを求めている。
特に慎重に吟味しなければならないのが、各部門間の連携である。このマーケティング・コンセプトによって、組織に関する提言が新たになされ、組織を変更しなければならないケースも多い。その結果、部門間には激しい対立や不安が生まれている。顧客の利益を最優先することを全部門が志向することで、利益が最大化するのかどうか、いまこそ問うてみるべきだろう。
ただし、本稿の目的はこのような問いに最終的な答えを出すことではない。顧客に好影響を与えるような社内の連携プレーを推奨することにある。そして、このような連携を図る際に生じかねない他部門とマーケティング部門との間の軋轢について指摘することでもある。
マーケティング部門にどれくらいの権限を与えるべきか
トップ・マネジメントが顧客志向を選択したならば、組織を挙げてこれを全面的にバックアップしなければならない。
なぜなら、それぞれが専門的な仕事に携わっている部門に分かれている組織では、顧客満足という目的について、各部門の活動と判断が直接的ないしは間接的に何らかの影響を及ぼしているからである。
概して、これらの影響力はばらばらに、独立している。しかし、新しいマーケティング・コンセプトの下では、一つに統合されることが望ましい。顧客満足は、マーケティング部門だけが管理しなければならないのではなく、さまざまな職能が総合的に作用して得られるものだからだ。マーケティング部門は、そのまとめ役を積極的に引き受けるべきだろう。
ただし、このような協調的マーケティングを実現するために、マーケティング部門が他部門にどれくらいの権限を有するべきかという問題になると、意見が分かれる。