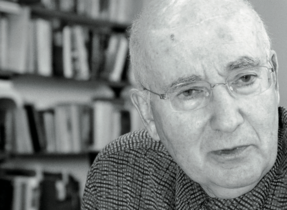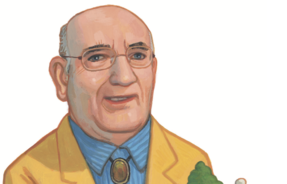-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
コラボレーションが閉塞状況を打破する
アメリカでは、音楽や演劇など公演芸術の非営利団体が危機に瀕している。20年近い大ブームに沸いた後、その盛況ぶりはすっかり影をひそめてしまった。
上り調子だった1960年代半ばから80年代半ばの20年間に、財団や企業などからの寄付は1500万ドルから7億ドル近くまで拡大した。このおかげで、プロとして活動するオーケストラの数は58から1000以上に、劇場付属の劇団も12から400以上に増えた。
なにしろ87年には、非営利の芸術団体が上げる興行収入はスポーツのそれを上回っていた。潤沢な資金を手にした芸術団体は意欲的な企画を次々に打ち出し、運営スタッフの数を増やし、収容人員の多い新しいコンサート・ホールや劇場を創設した。
中規模のオーケストラはこれまで、公演ごとにギャラを支払っていたが、初めて団員と年間契約を結ぶことができたのもこの頃である。このような待遇は、それまでは大都市を活動拠点とする大編成のオーケストラのメンバーに限られていたものだが、地方都市の楽団員も生活の保証が得られるようになった。
それもこれも、観客数と寄付金が右肩上がりで増え続けていくという、楽観的な空気が社会に蔓延していたからである。
ところがここ数年で、いくつもの大劇団や大オーケストラが公演を縮小せざるをえなくなった。なかには完全に活動を停止したところもある。観客数の減少と負債の膨張に襲われたのだ。
政府の補助金は大幅に削減され、自治体や民間財団などの出資者は特定公演にのみ寄付金を拠出するようになった。これでは維持運営費をまかない切れない。また支援するにしても、組織のスリム化、ビジネス・マインドの醸成、後援企業のマーケティングへの貢献といった条件つきとなった。
しかも時を同じくして、芸術団体は維持運営費の慢性的な上昇という問題に直面する。20世紀を通じて、企業は目覚ましい生産性の向上を実現し、コスト削減やダウンサイジングによって収益性を高めたが、公演芸術はそうはいかない。ベートーベンの第五交響曲を演奏するには相変わらず36分かかるため、最低70人からなるオーケストラが必要となる。観客動員数もよくて横ばい、大方は減少の一途をたどっている。
要するに、アメリカ人のライフスタイルが変わったのだ。アメリカ人の余暇時間は73年に週26.2時間だったが、87年には16.6時間と37%減少した。ベビーブーマーの世代が要職に就くようになったことや、共稼ぎ夫婦、片親家庭が増えたことが原因である。