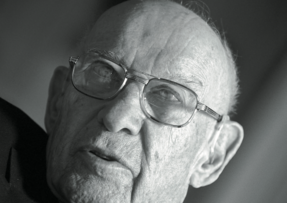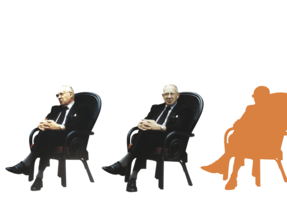-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
ナレッジ・デバイドは一時的な現象にすぎない
2003年8月、突き抜けるような晴天の昼下がり、カリフォルニア州クレアモントにあるドラッカー教授の自宅で本インタビューは行われた。94歳のいまもなお、その慧眼ぶりは依然健在であり、柔らかな物腰には賢者のゆとりが漂っている。
「物を書くために生まれてきた」教授は、インタビューにおいても常に的確な言葉を吟味する。そして、時にジョークを交えつつ、3時間にわたって明日の世界について語ってくれた。
その内容は、「上下」の2部構成として、今号と次号にわたってお届けする。今回は、知識社会のゆくえとそのなかに生きる個人に関する問題を中心に紹介する。また次回では、人口動態から予測する世界の動向と日本の課題について披瀝する。
DHBR(以下色文字):あなたが、知識が経済や企業を牽引していくと初めて指摘したのは、もう半世紀近く前になるでしょうか。そして『ポスト資本主義社会』で述べられたような現実が、インターネットの普及と相まって、ようやく一般にも認識されるようになりました。かつての工業社会では、先進国と発展途上国、富める者と富まざる者といったように、その進展と共に経済格差がもたらされました。知識社会でも同じような格差、いわば「ナレッジ・デバイド」が生じるのではないでしょうか。
ドラッカー(以下略):現時点では、これが拡大しているのか、縮小しているのか、何とも言えません。
競争のグローバリゼーションによって、知の二極分化、すなわちナレッジ・デバイドが広がっているかのように見えますが、はたして本当なのでしょうか。あるいはまったく逆かもしれません。
アメリカでは労働者階級の人々が教育を一種の資格ととらえているため、これまでナレッジ・デバイドが問題視されることはありませんでした。それに、ある程度の教育を受けた人に、そのぶん高い給料が支払われるのは公正で適切であると考えられています。
ただし、教育水準が全体的に高い日本では、これはやっかいな問題のはずです。日本の場合、60歳以下で見て、ほとんどの人たちが高校レベルの教育を修めていますが、アメリカでは近年まで、4割程度にすぎませんでした。つまり日本は、その知的生産性はともかく、その知識水準は相対的に高いわけですね。
つまり、そのような自信やおごりが自らの足をすくう可能性があるかもしれないわけですね。