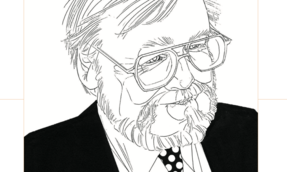-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
危機に備えているのは「フォーチュン500」のわずか5%足らず
この1年半の間、同時多発テロからタイコ・インターナショナルの不祥事まで、実にさまざまな危機に見舞われた。これらは、企業に危機管理の見直しを迫るものだった。
以前よりリスク・マネジメント・プログラムを備えている、リスク感度の高い企業では、さっそく見直しを図り、改善や補強を加えている。具体的には、過去5年ないし10年に起こった事件について、原因を分析し、コストを算定し、再発のリスクを再評価したのである。
しかし、このような教科書どおりの備えだけではまだ不安が残るという企業も少なくない。
率直に言って、いまの世のなか、これまでの危機管理手法だけでは万全とはいえない。一つ肝心なもの、すなわち、さまざまな危機を包括的かつ総合的に検討することが欠けているのだ。
これまで大多数の企業が改善に改善を重ねてきた危機管理手法は、過去に遭遇したことのある緊急事態に対処するものでしかない。しかし、初めて出会うような類の危機、さらには想像を超えた災厄のほうが危険はずっと大きい。かくして「昔の戦略で次なる戦争に臨む」といった状況は依然変わっていない。
これは一部の企業に限られた問題ではない。南カリフォルニア大学のクライシス・マネジメント・センターでは、20年間にわたって「フォーチュン500」各社の危機管理体制について観察してきた。その主たる手段は、上場未上場を問わず、各企業の危機管理に関する内部監査であり、定期的な調査である。この20年間の調査から有意義な原則が導き出されるものと、我々は確信している。
調査対象企業は大きく2つに分けられた。「危機に強い(予防的に動く)企業」と、「危機に弱い(場当たり的に動く)企業」である。
後者の「対処型」企業は、すでに経験した類の有事に備えるにとどまり、しかも完璧とは言いがたい。一方、前者の「予防型」企業は、過去に経験した緊急事態のみならず、より広範な危機に対処するプログラムを作成している。このギャップを埋めることはさして難しくはない。しかし、前者と後者とでは雲泥の差がある。