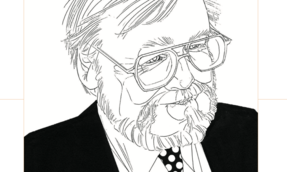-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
組織は予測不可能な試練に直面している
ほとんどの人々が、家庭や教会、学校、企業など、何らかの組織に所属している。そして、親しい間柄の人たちに対してそうであるように、このような集団に対しても、それにまつわる状況の多くを当たり前のこととして、気にも留めていない。
我々はこのような集団に慣れ親しんでしまっているがゆえに、ある種の憤りを感じたりすることもよくある。気の滅入るようなルーチンワークを課して、人間性を押し殺してまで順応するように求める組織をいまいましく思い始めるのだ。
心のどこかで、我々はこう信じている。組織はきわめて画一的で予測可能であり、メンバーたちを変わり映えしない課題に1年中向かわせ、コツコツと単調に仕事をこなさせる──。
しかし、こうした考え方は根本的に間違っている。多くの組織は、予測不可能の、あらゆる規模や種類の試練に直面している。これらが重なると、人々の創造性や想像力が大いに求められる。
実際、たえず変化を続け、波乱に満ちた事業環境においては、企業は安定した確実な存在であるという前提は危険である。いざ予測不可能な事態が生じ、見慣れた世界が崩れ去ると、我々は麻痺状態に陥り、事態を切り抜けることができなくなる。
では、予測不可能な事態について認識を深め、より適切に対処するにはどうすればよいのか。
この質問をぶつけるのにカール E. ワイクほどふさわしい人物はいない。ワイクは、ミシガン州アナーバーのミシガン大学ビジネススクールで組織行動学および組織心理学のレンシス・リカート特別講座の教授を務めると共に、同大学の心理学教授でもある。その研究過程で、組織内の人間が特定の行動を取る理由を鋭く考察し、世界的に知られるようになった。
1969年に上梓された『組織化の社会心理学』(文眞堂)では、それまでの組織心理学の常識を覆し、混沌の利点を称える一方、計画立案の落とし穴を指摘し、「センスメーキング」の効用を説いた。
こうした洞察は、後の著書『センスメーキング・イン・オーガニゼーションズ』(文眞堂)でさらに深められている。最近では、ミシガン大学の同僚キャサリン M. サトクリフと共に『不確実性のマネジメント』(ダイヤモンド社)で、不測の事態への対処法に目を向けている。