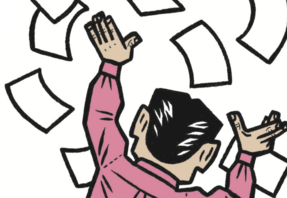-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
-
PDFをダウンロード
Bクラス社員を再評価しよう
ヘッドハンティング合戦が耳目を集めるなか、各社がスター人材の獲得と維持に多大な時間と金と労力を注いできたのも意外ではない。
CEOの多くは、同じ採用活動ならば、スター人材を相手にしたほうが気分はよい。なぜなら、面接相手の若いスター人材たちは、往々にして若き頃の自分を思い出させるからで、また彼らの才気と意欲が周囲を感化し、もっと一緒にいたいと思わせるからでもある。しかも、景気が低迷し、企業破綻が相次ぐ昨今、業績を好転させるのに必要な何かを備えていそうな人材からは、抗しがたい魅力が漂ってくる。
我々がスター人材に夢中になるのも無理からぬことだが、ともするとそのせいで、脇役的な人材の重要性を見過ごしてしまうおそれがある。
たしかにAクラス社員は業績に大きく貢献しうる。しかし、20年にわたるコンサルティングや調査、あるいはセミナー活動から、喝采を浴びることのないBクラス社員の重要性に気づいた。実際、長期的に業績を伸ばせるかどうか、またそもそも存続できるかすら、彼らの努力や献身に負うところがはるかに大きいのだ。
このような人材はそれなりの能力を備え、しかも地道な努力を続ける人々であり、いわば産業界の最優秀助演俳優なのである。
大手コングロマリットの油田でマネジャーを務めていたアイバン・ファーマーの例を見てみよう(本稿で取り上げる事例はすべて実話のため、人名および社名等は仮称とする)。
アイバンは内心、部下のBクラス社員たちが「ロケット野郎」(石油業界ではいつでも、どこにでもすぐ転勤に応じ、出世の階段を上り詰めていく人々のことを、俗に「ロケット野郎」と呼ぶ)でないことに失望を感じていた。Bクラス社員たちは野心に欠け、したがってアイバンたち経営幹部と同類ではなかった。「だから彼らを見くびるようになったのだ」とアイバンは後にはっきりと認めている。
アイバンは腰の重い彼らを評価しなかったが、中堅のBクラス社員たちが一つの油田で働き続ける最大の理由は、チーム内の仲間意識や安心感を喜びとしていたからだった。