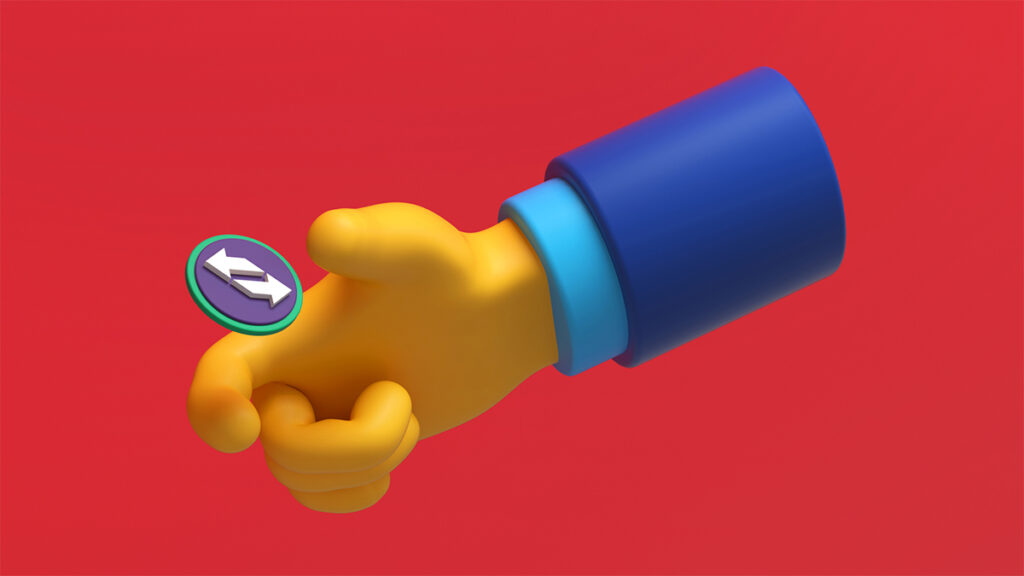
-
Xでシェア
-
Facebookでシェア
-
LINEでシェア
-
LinkedInでシェア
-
記事をクリップ
-
記事を印刷
ピボットする能力が強みから弱みに変わる時
いまの時代に最も称賛されるリーダーシップ特性の一つに、「ピボットする能力」がある。これは、予定していた計画が阻まれたり、不利益が生じることが判明したりした際に、素早く進路を変更する能力だ。
この手の迅速な適応力はアジリティと呼ばれることも多く、急速に変化する環境、あるいは旧来の行動やマネジメント手法が通用しない未知の領域でイノベーションを起こす際に極めて重要となる。アジリティをリーダーシップのスーパーパワーと見なす人もいる。
だが、いかなるリーダーシップのスーパーパワーも、弱みに変わるおそれがある。リーダーがプロジェクトの方向性を頻繁に変更すると、部下は自分がすべきことがわからなくなり、少なくとも、計画の見直しと対応に時間を割く必要に迫られ、効率が悪化して混乱が生じ、進歩が妨げられる。
さらに、モチベーションも低下する。まるで、「北に向かって走れ」と指示されたのちに、「南へ行け」「いや、北だ」「やぱり南へ」と告げられるようなものだからだ。何度も軌道修正が繰り返されるうちに、従業員はリーダーの方針が固まるまで何もせずに待つのが最善、と考えるようになってしまう。
この問題を解決するには、単にアジリティを低下させればよいというわけではない。こうした事例に登場するリーダーはおおむね、目まぐるしい変化が続き、不確実性の高い状況下で正しい行動を取っている。行き止まりの道や、会社の時間とリソースを浪費する道に固執することなく、より生産的だと判断した方向に向けてチームをピボットさせ、必要に応じて何度も軌道修正を繰り返すのだ。
筆者は、イノベーションと効率化について企業にアドバイスをしてきた長年の経験から、ピボットによってチームを率いるリーダーは、そこから生じる悪影響に対処するために、「手段」と「目的」を明確に区別すべきだと確信している。ゴールに至るための手段は変更しても、最終的なゴールは不変であることを明確に伝える必要がある。
2つの事例を見てみよう。筆者がアドバイスをしたあるハイテクベンチャー企業では、創業者が実験的な試みと臨機応変な対応を繰り返しながら主力製品をつくり上げ、最適な方法が見つかるまで試行錯誤を繰り返していた。しかし、会社が100人以上のエンジニアを抱える規模に成長し、複数のプロジェクトチームがオリジナルの製品設計に携わるようになるにつれて、行き当たりばったりで方針を変えたがる創業者の存在は、強みではなく弱みになっていった。
あるマネジャーは、当時の状況を、全員が次の指示を待つだけの一種のマヒ状態に陥っていた、と表現した。「誰もイニシアティブを取ろうとしません」と、彼女は語った。「何をやっても、たいてい変更されてしまうからです」
こうした「アジリティ過剰」のダイナミズムは、小規模のスタートアップにも、大企業にも共通する課題である。





![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)









