名和氏は、自分の中にある本来の強みから、そこに織り込まれている未来の自分を新しく紡ぎ出していくのが真の変革だと説く。そして、その変化を、流行理論の仮面をかぶるだけの「変身」ではなく、「変態」と位置づける。
それには、伝統と革新を分けず、両者をたえず行き来することが肝要となる。名和氏によれば、「既存事業」と「新規開拓」を別々に行うのは両利きの経営の誤った解釈だ。
では、コンサルティング企業(コンサル)はそのサポートをするのにどのような役割を果たすべきなのか。名和氏は、パーパス経営のアドバイザー、イノベーションスケール化のパートナー、変革のカタリストの3つの役割を挙げる。順番に見ていこう。
「まず、企業がみずからの思いでつくりたい未来を内発的につくる支援をすることです」
企業の中にある顕在化していない未来を一緒に探る。パーパス経営で重要な、企業にとっての「ワクワク」「ならでは」「できる」を満たすMTPをともにつくるアドバイザー役になることが第1の役割だ。
その際、コンサル視点の変革のベストプラクティスを“ご託宣”して押しつけるのではなく、組織に備わる静的、動的DNAの2つを再起動する。この2つが組織の伝統の進化を生み出すからだ。
静的DNAは、企業の本質、アイデンティティだ。外圧に侵されず、その企業らしさを再現できる力、免疫のようなものでもある。他方、動的DNAは、自己否定をし、変化を自分の中に取り込んでいく力だ。動的DNAを見つけるのは難しいが、時間軸と空間軸をずらすことで見えてくると名和氏は言う。
「時間軸をずらし、過去に企業が変化した際、どんなトリガーがあり、どのような変化を起こしたのかを検証すると、そこで発揮されているのが動的DNAです。空間軸をずらすとは、本社やコア事業の周囲、グループ会社、海外、ノンコアビジネスに変化のタネが潜んでいるのでそれを見出すということです。2つのDNAをコンサルが引き出すことが求められています」
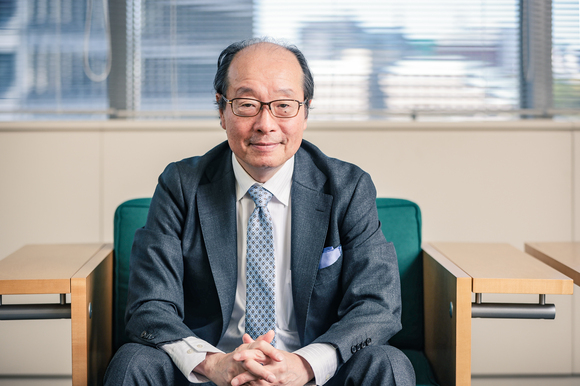
一橋大学ビジネススクール 客員教授
名和⾼司氏
東京大学法学部卒、三菱商事勤務ののち、ハーバード・ビジネス・スクール(HBS)修士。マッキンゼー・アンド・カンパニーで約20年間コンサルティングに従事。デンソー、ファーストリテイリング、味の素などの社外取締役を歴任。『パーパス経営』『学習優位の経営』『10X思考』など著書多数。
日本企業が苦手なスケール化を支援する
2つ目に期待されるのは、イノベーションをスケール化するパートナーとしての役割だ。
「新規事業において、0‒1はむしろやさしいのですが、本当に難しいのは1‒10のマネタイズ、10‒100の社会実装のフェーズです」
実際、伝統企業の新規事業、デジタルラボはいくらでもあるが「やっているつもりなだけで、事業化につながるものがほとんどありません」。海外事例の研究を蓄積するコンサルは、マネタイズ、社会実装について適切に指南できるはずだ。
そして実際に新規事業のプロジェクトに伴走するために、傍観者で終わらず、同じ船に乗る当事者として、コンサルもエクイティを持ち、人を送り込むことも増えてきている。パートナーとして、ジョイントベンチャーを設立する、あるいは、利益が出る可能性が見えた段階でフィーをもらうプロフィットシェアリングという手法も有効だ。
資金だけでなく、人財についても、実行力をうまくクライアント側に伝授するために、人財教育・強化を支援する。たとえば、コンサルには新入社員を短期間で一人前にするノウハウが豊富にある。これを応用するのだ。
「とはいえ企業にとって変革はつらいもの」と名和氏。