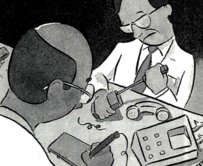GM vs. フィッシャーボディ
1919年、GMはすでに米国を代表する自動車メーカーだった。当時の自動車産業は、木製部品を組み合わせて車体をつくる「オープンな車体製造」から、1枚の鉄板をプレスする「クローズドな車体製造」への移行期にあった。プレス製造には、多額の設備投資が必要になる。そこで、GMは当時有力サプライヤーだったフィッシャーボディに、プレス設備の導入とクローズドな車体の製造を依頼した。
しかし、多大な費用のかかるプレス設備の導入を、フィッシャーボディが簡単に受けるはずがない。そこでGMは「フィッシャーボディが設備投資をしてくれたら、今後10年は車体を同社以外からは受注しない」という専売契約を結んだ。結果、フィッシャーボディは設備を導入し、同社によるクローズドな車体のGMへの供給が始まった。
ここで「不測の事態」が起こる。まず、その後数年の間に、米国内の自動車需要が想像できなかったほど急激に伸びたのだ。さらにその需要の大半は、従来の木製自動車ではなく、プレス技術が必要な「クローズドな鉄鋼車体」の自動車だったのである。
この想定外の市場の伸びを受け、GMはフィッシャーボディにクローズドな車体の大量発注を申し出た。そして大量発注をすれば規模の経済効果でコストダウンが可能だろうから、当然ながら車体価格の値下げも期待した。しかし実際には値下げは成立せず、GMはフィッシャーボディから高価な車体を購入し続けることになった。GMにとって非常に不満の大きい状況に陥ったのである。
なぜGMはフィッシャーボディに値下げを強制できなかったのか。それは、急激な需要変化での価格対応について、両社の間で明快な取り決めが契約でなされておらず、さらにGMがフィッシャーボディ以外に車体供給先を見つけられなかったことが大きい。
そもそも両社は10年の専売契約を結んでいるから、GMは車体供給元の変更が難しかった。しかしより深刻なのは、GMに必要な「クローズドな車体製造の技術・ノウハウ」が、すべてフィッシャーボディ側に蓄積されていたことである。
したがって、仮にGMが違約金を払ってフィッシャーボディとの契約を破棄しても、GMは同社ほどに自社の求める技術を持ったサプライヤーを見つけられない。フィッシャーボディもそれはよくわかっているから、値付けにおいて「足下を見てきた」のである。
このGMが陥った状況を、経済学・経営学では「ホールドアップ問題」という。
取引費用理論で企業が直面する問題が、このホールドアップ問題だ。次回はホールドアップ問題の解説と、解決について説明する。
【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】
取引費用理論(TCE)
エージェンシー理論
情報の経済学
【著作紹介】
世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。
その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。
本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。
お買い求めはこちら
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※1 組織の経済学に関する参考書は第5章注1を参照。
※2 現在の組織の経済学では、TCEと関連した理論として資産権理論(property rights theory:PRT)が発展している。TCEが取引ガバナンスに着目するのに対し、PRTでは複数のプレーヤーがともに投資する資産から事後的に残余権(residual rights)が発生した時のプレーヤー間の衝突と、それを踏まえての事前の資産権の配分に焦点が当たる。PRTは経済学で発展しており、近年は経営学でも応用が始まっている。しかし、この動きはまだ端緒についたばかりであることから、本書ではTCEのみを取り扱うことにした。PRTについては、例えばマサチューセッツ工科大学の経済学者ベント・ホルムストロムの一連の研究を参考にされたい。TCEとPRTの違いについて経済学者が著した論文には Gibbons,R. 2005. “Four Formal (izable) Theories of the Firm?” Journal of Economic Behavior & Organization, Vol.58, pp.200-245. がある。経営学者が両者の違いを著したものには、Mahoney, J. T. 2004. Economic Foudations of Strategy, SAGE Publications. に加えて、Kim, J. and Mahoney, J. T. 2005. “Property Rights Theory, Transaction Costs Theory, and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategic Management,” Managerial and Decision Economics, Vol.26, pp.223-242. がある。
※3 コースの著作の中では、本文でも紹介する Coase, R. 1937. The Nature of the Firm, Economia. があまりにも有名だ。他にコースの代表的著書として、Coase, R.1988. The Firm, the Market, and the Law, University of Chicago Press.を挙げておく。ウィリアムソンの著書には、Williamson,O.E. 1975. Markets and Hierarchy, Free Press. や Williamson, O. E. 1985. The Economic Institutions of Capitalism, Free Press.、Williamson, O. E. 1996. The Mechanisms of the Governance, Oxford Univ Press. がある。
※4 Williamson, O. E. 1975. Markets and Hierarchy, Free Press.
※5 このように「限定された合理性」は人間の認知に焦点を当てており、したがってそのルーツは、ハーバート・サイモンらが発展させた認知心理学にある。サイモンの理論は本書第2部で紹介していくが、このように他の学術分野で生み出された「人間についての仮定」を取り込むことで、経済学も発展しているのである。
※6 ここではKlein, B. 1988. “Vertical Integration as Organizational Ownership: The Fisher Body-General Motors Relationship Revisited,” Journal of Law, Economics, and Organization, Vol.4, pp.199-213.より主要なポイントを抜粋し、筆者なりの言葉で紹介している。この事例は同論文で紹介されて以来、TCEの説明に頻繁に使われる。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)