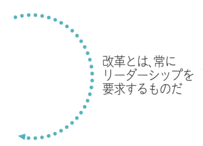(2)表出化(externalization):暗黙知→形式知
個人間の暗黙知を対話・思索・メタファーなどを通して、概念や図像、仮説などをつくり、集団の形式知に変換する
共同化を経て共有された暗黙知は、そのままでは使えない。暗黙知は形式知化されることで初めて顕在化し、より多くの人に使われる。「言語化」はその代表だろう。言語とは、我々が内面に持っている暗黙知のごく一部を表層化させたものだからだ。したがって求められる暗黙知が変われば、新しい言語が形式知として生み出される。
例えば、「エモい」という言葉がそうではないだろうか。一時期、若者を中心にかなり使われていた言葉だ。実は筆者は、このエモいの意味がいまだに理解できない。ネットで初めて見た時も意味がわからず、検索して調べたが、「興奮した、みたいな感じ」「感情が高ぶって、感情的になること」「この音楽エモい、とか」などと書かれているだけで、まったく理解できない。
すなわち、社会人大学院の教員で20代以下の若者と日常の交流がない筆者は、そもそも「エモい」の感覚・暗黙知が「共同化」できていないのだ。一方の若者たちは日頃の共同体験からその感覚を共同化できているので、「エモい」という形式知を生み出すことができるのである。
では(仮に共同化まではできたとして)、この表出化フェーズ(暗黙知→形式知)で効果的なものは何だろうか。ここでは3つ挙げてみたい(3つのうち最初の2つは野中自身が、最後は筆者が提示するもの)。
比喩(metaphor)、類似推論(analogy)
一つは、メタファーやアナロジーなどの重要性である。暗黙知は言語化されていないのだから、まずはそれに近しいもの(比喩・たとえ)で代替し、相手にイメージを共有してもらうのだ。実際、イノベーティブな経営者には、メタファーやアナロジーの達人が多い。ソフトバンク創業者の孫正義氏や、日本電産の永守重信氏はその代表格だ。
例えば永守氏は、自身の経営手法を「千切り経営」と呼ぶことがある。「何か問題があったら、包丁で千切りするように事象を細かく刻んで分析せよ」ということだ。おそらく、実際には永守氏に体化されている知は、それ以上に圧倒的に深いものがあるに違いない。ただ、その大部分は暗黙知化されたままなので、まずはそれを「千切り経営」と比喩しているのだ。
アブダクション(abduction)
暗黙知から「仮説化」を行うことが、アブダクションである。「『A→B』なのではないか?」といった関係性で、形式知化することだ。例えば、もしこの世に「A→B」という真理法則があった時、仮に「A→」の部分がわかっていなくても、Bという現象が起きた時に、「これは「『A→』が理由ではないか?」と気づくことだ。
筆者は、いわゆる「ハッとした気づき、閃き」に近いものと理解している。例えば、ニュートンが木から地面に落ちた林檎を見た時に、「これは地球の重力に引かれているからではないか?」と思いつくことだ※7。ここで「A→」が本当に正しいかは、問題ではない。「A→」の可能性に気づくことが、重要なのだ。
野中によると、アブダクションに必要なのは「目的意識を持っての、徹底的な事実の察知」である。最近の著書『直感の経営』で野中は、例えば富士フイルムを化学メーカーに大転換させた古森重隆氏などを引き合いに出しながら、「優れた経営者ほど現場の事実を大事にし、事実をありのままに徹底的に見ようとする」といった主旨のことを述べている。その時に「ハッ」とした気づきがあるのだ。
デザイン思考
アブダクションが暗黙知を仮説化することだとすれば、暗黙知を図像化することがデザインだ。こう考えると、現在のデザイン思考ブームも理解いただけるのではないだろうか。多くの企業・経営者が、暗黙知の形式知化を求めているからである。デザイン思考分野で注目を集める佐宗邦威氏は、デザインとは、「暗黙知を形式知化すること」と断言する。
その佐宗氏が率いる戦略デザインファームBIOTOPEは、いま大手企業からのプロジェクトの依頼が後を絶たない。公表されているだけでもNTTドコモ、ぺんてる、東急電鉄、山本山、日本サッカー協会などの案件を手がけている。いま日本の大きな組織で起きていることは、「自社の方向性がわからない」「存在意義が言語化できない」「創業理念をアップデートできない」などだ。経営理念は会社の「信条」であり、したがって実は暗黙知的な側面が強い。BIOTOPEが得意とするのは、それをデザイン思考の手段などを使いながら形式知化していくことであり、だからこそ大手企業から引く手あまたなのだ。
【動画で見る入山章栄の『世界標準の経営理論』】
組織の知識創造理論(SECIモデル)
知の探索・知の深化の理論
組織の記憶の理論
【著作紹介】
世界の経営学では、複雑なビジネス・経営・組織のメカニズムを解き明かすために、「経営理論」が発展してきた。
その膨大な検証の蓄積から、「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた「標準理論」とでも言うべきものが、約30ある。まさに世界の最高レベルの経営学者の、英知の結集である。これは、その標準理論を解放し、可能なかぎり網羅・体系的に、そして圧倒的なわかりやすさでまとめた史上初の書籍である。
本書は、大学生・(社会人)大学院生などには、初めて完全に体系化された「経営理論の教科書」となり、研究者には自身の専門以外の知見を得る「ガイドブック」となり、そしてビジネスパーソンには、ご自身の思考を深め、解放させる「軸」となるだろう。正解のない時代にこそ必要な「思考の軸」を、本書で得てほしい。
お買い求めはこちら
[Amazon.co.jp][紀伊國屋書店][楽天ブックス]
※7 実際にはこのリンゴの逸話は虚構であるようだが、あくまで喩えとしてここでは使っている。







![H.ミンツバーグ経営論[増補版]](https://dhbr2.ismcdn.jp/mwimgs/8/7/135w/img_871cd4da49e5d4f957c01d18842ab79034921.jpg)